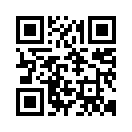2025年05月10日
GX志向型住宅が2,500万円から建てられる
物価高で、家なんてもう無理…と感じていませんか?
お米や日用品など、暮らしに欠かせないものの値上がりが続き、「今の時代に家を建てるなんてとても無理…」と考えている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、国は「2050年カーボンニュートラル実現」に向けて、住宅の高性能化を本格的に推進。
2025年4月からは省エネ基準の義務化がスタートし、2030年にはさらに一段上の基準が導入される予定です。
エネルギー価格が高騰し、暖房さえ満足に使えないような生活にはもう戻れません。
だからこそ、今注目されているのが**最大160万円の補助金が受けられる「GX志向型住宅」**です。
**GX志向型住宅**については以前詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
GX志向型住宅補助金とは?
2025年4月に始まったばかりの新制度で、全国一律、性能基準を満たした住宅に対して最大160万円の補助金が支給されるというもの。
ただし、補助を受けるには一定以上の高性能住宅であることが条件。
そのため、「どれくらいの価格でその基準を満たせるのか?」という質問が多く寄せられています。
LaCoupe(ラ・クープ)で補助金対象住宅を実現
当社がご提案するセミオーダー住宅「LaCoupe(ラ・クープ)」は、GX志向型住宅補助金の対象仕様に対応しています。
間取りのイメージを簡単に描いていただくだけで、お見積りも可能です。
以下は、実際のプランの一例です:

この住宅は次のような高性能を備えています。
これらを満たした上で、160万円の補助金が適用可能です。
性能だけじゃない、設備にもこだわりを
「価格を抑えるために安価な建材を使っているのでは?」と思われるかもしれませんが、LaCoupeではそういった妥協はしていません。
当社の注文住宅で採用している建材・設備の中から、性能・デザイン・コストのバランスが取れた優れた製品だけを厳選しています。

特に注目していただきたい2つの設備
① 熱交換型ダクト式換気システム
室内の温度を保ったまま換気できるため、冷暖房のエネルギー損失を抑え、光熱費を削減します。
② 床下エアコン(全館空調)
たった1台の壁掛けエアコンで家全体を暖める、高気密・高断熱住宅ならではの革新的設備。
床暖房のように床面が熱くなりすぎず、小さなお子さまにも安心です。
LaCoupeではこの2つを標準仕様として搭載しています。
今こそ、次世代の高性能住宅を補助金で手に入れるチャンス
GX志向型住宅は、今後の住まいの「新しい当たり前」になっていくでしょう。
LaCoupeなら、性能・快適性・価格のバランスが取れた高性能住宅を、補助金を活用してより現実的な価格で実現できます。
気になる方は、GX志向型住宅について詳しくまとめた別記事もぜひご覧ください。
あなたの家づくりの第一歩を、サポートさせていただきます。
「セミオーダー住宅」についてはこちらをご覧ください。☘️
2025年04月20日
リノベで2重屋根工法②
今回は工事の続きとして、断熱と通気を行う2重屋根の仕組みを解説します。
築33年の屋根から見えた「下地の重要性」
築33年を迎えた木造住宅の屋根葺き替え工事を通して、「屋根が住宅の耐久性にとっていかに重要か」を改めてご理解いただけたのではないでしょうか。
今回は屋根材をすべて撤去し、その下にある防水紙(アスファルトルーフィング)も剥がした状態で、屋根下地の状態を丁寧に確認しました。

下地には経年の汚れこそあったものの、大きな損傷や腐食はほとんどなく、非常に良好な状態でした。
(※もし下地に劣化が見つかった場合には、当然その箇所の補修が必要となります)
そのため、今回はこのまま既存の合板下地を活かし、新たに防水層を施工することにしました。
透湿防水シート「タイベック ルーフライナー」の採用

新たに張るのは、米国デュポン社製の「タイベック ルーフライナー」。
これは透湿性を持つ屋根用防水シートで、湿気を逃しながら雨水は通さないという優れた性能を持っています。
(透湿性とは、内部からの水蒸気を通し、結露を防ぐ機能のことです)
今回採用している「二重屋根工法」では、この防水層が3層構造となっており、タイベックルーフライナーはその3層目にあたる透湿防水層となります。
断熱工事で夏の暑さ対策も同時に

今回は、屋根材の交換だけでなく、夏の暑さ対策として断熱工事も同時に施工しています。
使用したのは、厚さ9cmのアルミシート付き断熱材(アキレスQ1MAボード)です。
このアルミシートが太陽熱の主成分である赤外線を反射し、上部に設けた通気層から熱を屋外へ逃がす構造です。
通気層は厚さ3cmの木材で確保し、その上に構造用合板を張って新しい屋根下地を形成しました。

通気のために木材を挟みます。

その後、新しい合板を張って屋根の下地が賛成です。

仕上げに2次防水層としてアスファルトルーフィングを施工
最後に、アスファルトルーフィング(防水紙)を再度施工し、屋根下地が完成しました。
このアスファルトルーフィングは、屋根材の下で雨水の侵入を防ぐ「2次防水層」として重要な役割を果たします。☘️

(※アスファルトルーフィングに透湿性はありません)
2025年04月13日
リノベで2重屋根工法①
隈研吾さんは、木材を大胆に外部に使った建築で知られ、多くの注目を集めてきました。ただ一方で、近年は各地の作品で木の劣化が進み、補修に多額の費用がかかっていることも話題になっています。
私たちのように木造建築に日々携わっている者にとって、無処理の木材を外部にそのまま使うことには大きなリスクがあると感じています。一般的な木材であれば、屋外にさらされると10年もしないうちに劣化が始まってしまいます。
たとえばウッドデッキに使用されるアイアンウッド(イペなど)のような非常に硬く耐久性のある木材であっても、15年ほどで傷みが目立つようになります。
屋根こそ、住宅で最も過酷な環境にさらされる場所
住宅の中で、最も厳しい環境にさらされているのが「屋根」です。雨や日射に常時さらされ、温度や湿度の変化も大きく、屋根材には高い耐久性が求められます。
そのため屋根材選びはもちろん重要ですが、実はその下にある「防水下地材」の性能こそ、構造材(木材)を守る鍵なのです。以前のブログでもご紹介しましたが、当社ではタジマ社のニューライナールーフという高性能な防水下地材(アスファルトルーフィング)を採用しています。やや高価ではありますが、それに見合う信頼性があります。
築33年の屋根をリノベーションして見えてきたもの
今回、築33年を迎える木造住宅にて、「二重屋根工法」を用いたリノベーションを実施する機会がありました。
実際に既存の屋根を解体することで、30年以上経過したアスファルトルーフィングがどのような状態であるのか、現場で直接確認することができました。
この工事の様子を、2回にわたってご紹介していきます。
このお宅では、33年の間とくに問題はありませんでした。しかし最近になって屋根材の劣化が目立ち始めたこと、そして使用されている屋根材がアスベスト含有製品であったことから、屋根の葺き替えを決断されました。

約30年前は、アスベストを含んだスレート系の屋根材が「カラーベスト」という商品名で広く普及しており、多くの住宅で使われていた時代です。
アスベスト含有の屋根材を改修する方法には大きく2つの選択肢があります。
・既存の屋根材をすべて撤去して新たに葺き直す方法
・既存の屋根の上から新しい屋根をかぶせて封じ込める「カバー工法」
今回は後者のカバー工法ではなく、将来的な負担を残さないことを優先し、屋根材を撤去してから新たに葺き替える方法を採用しました。
アスベストを含む屋根材を解体する際には、本来であれば屋根材を極力破壊せずに撤去することが望ましいとされています。
しかし今回の現場では、基材自体が経年劣化しているうえに、屋根下地にしっかりと張り付いた状態だったため、どうしても「剥がし取る」ような作業にならざるを得ませんでした。
廃材は専用の処理バッグに、手作業で少しずつ収めて地上へ降ろします。手間と時間のかかる作業でしたが、安全と法令遵守のためには避けて通れません。
その分、作業全体の時間は通常より大きくかかってしまいました。

撤去後、下地のアスファルトルーフィングを確認すると、ところどころに穴が開いている箇所が見受けられました。
特に、屋根材が重なり合う部分の真下では、長年の摩擦による擦れが顕著です。
屋根材は気温変化によってわずかに伸縮を繰り返します。
そうした動きが30年以上続いたことで、防水層との間に摩耗が生じていたと考えられます。
実際に間近で見ると、このような状態でした。

さらに詳しく観察すると、下地の合板が露出している箇所もところどころ見られました。
築30年以上の住宅では、多かれ少なかれこのような劣化が進んでいる可能性があると言えます。
今回の現場では、幸いにも下地の構造用合板に大きな傷みは見られませんでした。
ぎりぎりのタイミングで補修できたのではないかと思われます。

これまでの日本の住宅は、概ね30年を目安に建て替えるケースが一般的でした。
しかし、今後のように30年を超えて住み続ける場合には、屋根の下地材――特にアスファルトルーフィングの耐久性が重要になってきます。☘️
2025年04月06日
さいたまの住宅会社の法令違反について
小屋裏の石膏ボード未施工は違反?
建築基準法と例外ケースを解説
通常、小屋裏は「木材むき出し」でも違反にならない

違反の可能性がある「特定の条件」とは?
1. 省令準耐火構造や準耐火建築物として販売されていた場合
住宅が「省令準耐火構造」として販売されていた場合、火災時の延焼を防ぐ目的で、小屋裏へ通じる気流が起きないようファイアーストップ構造とするなどの施工をする必要があります。この仕様は 建築基準法施行令 第136条の2 や告示で定められています。※ 2×4工法は全棟が省令準耐火構造になります。
2. 特定の外壁材で建築されている場合
建築地が防火地域・準防火地域でなくても、都市計画区域では屋根や外壁だけでなく小屋裏も延焼防止対象とされ、内装制限の対象になることがあります。これは、外壁の防火認定において外壁材そのものでなく、内部の石膏ボードや断熱材も込み(外壁構成)で認定を受けている場合に起こる可能性があります。
3. 契約時に防火性能や断熱性能が明記されていた場合
パンフレットや契約書に「省令準耐火仕様」や「断熱性能〇等級」などと明記されていたにもかかわらず、それに準じた施工がなされていなければ、契約不履行や景品表示法違反の問題に発展します。今回の教訓:見えない部分こそ注意が必要
購入者・施工者ともに、カタログや契約内容に記載された性能と実際の施工が一致しているかを確認することが重要です。
まとめ
- 通常の住宅では、小屋裏の木材表しは建築基準法に違反しない
- 省令準耐火や都市計画区域の延焼抑制など、仕様や地域条件によっては不燃材での仕上げが必要
- 見えない箇所の施工不備がトラブルや違反につながることがある
仕様通りの家づくりがされているか、細部まで確認する意識が2025年4月以降ますます重要になります。☘️
2025年03月29日
2×4工法と許容応力度計算
変わる所はいくつかあるのですが、中でも「4号特例の
縮小」が、当社メインである木造住宅に大きく拘わるので影響が大きいです。
屋根に載る太陽光パネルや窓ガラスの多重化による
重量増に対応するため、構造根拠の提出が必須になりました。
俗にいう構造計算が必要になると言われる所以です。
この構造計算ですが、許容応力度計算という手法が
一般的で、構造の先生にお願いして計算して戴く必要があります。
(自前でソフトウェアを買って計算することも出来ますがハードルが高い。)
2×4工法と壁量計算は相性が良い
ただ、今までの方法が無くなったわけではありません。
それは壁量計算と呼ばれるもので、品確法の耐震等級3を取得できます。
「品確法の」と付ける理由は、「許容応力度計算の」
耐震等級3と区別する為に構造塾さんなどが流行らせた言い方で、
国とすれば同じ耐震等級3で区別はないはずですが…。
その為「許容応力度計算の」耐震等級3のほうが上位にある印象になっています。
2×4(ツーバイフォー)工法は日本語で枠組壁工法と呼びます。
木質パネルの壁工法と言い換えると解りやすいかも知れません。

要は、パネルの組合わせで6面体を作り、6面体の組み合わせで建物を形作る工法です。
部材は標準化・規格化されていて一つ一つの部材の強度も明確になっています。
また、配置バランスや開口部の上限などもルール化され、力の伝達・構造解析が容易です。
ですから、必要な量の壁を適切な位置に配置することで高耐震の建物になります。
必要な量の壁を適切な位置に配置=壁量計算なのです。
2×4工法と壁量計算は相性が良いのです。
今回の建築基準法改正では壁量計算もより厳格になり、
個々の建物の大きさ重さや積載荷重も含めた全体の重量を考慮し、壁量を求める方法に変わりました。
この改正に合わせて、
2×4工法の計算ソフト「らくわくVer2」もリリースされ
早速使ってみた所、使い勝手も良く、結果にも大きな変化がありませんでした。

改正後もスムーズに仕事ができると確認できました。
改正点は主に3つ
1.壁量計算のため床面積に乗ずる数値を邸別に代入
2.壁倍率をmax5倍から7倍に
3.垂れ壁や腰壁も条件により準耐力壁として計上可能
(らくわくは壁量計算で間取りを解析しますが、個々の梁や基礎構造は許容応力度計算を行っております。)
一方、在来工法は無数の部材を自由に使える為、
その部材の組み合わせで作られた建物がどの程度の強さか?には解析が必須です。
その為「許容応力度計算」が必要になります。☘️
2025年03月23日
今、住宅に求められるコト
デフレが30年も続いた日本には、インフレ時代に合わない習慣が数多くあります。
例えば、貯金。
お金の価値(同じ金額で買えるモノ)がドンドン安くなってゆくので、銀行に預けていては、価値が目減りするだけです。
例えば、借金。
借りた金額の価値が年々減少して行くなら、借入も有利と言えるかも。
インフレで金利上昇もありますが、特に住宅ローンは5年間は据え置きです。
この様にこれからの時代、インフレのマインドを持つことが必要です。
注文住宅について考えてみましょう。
2025年4月に始まる性能義務化と4号特例の縮小で、
インフレ+性能向上仕様+申請手数料UPのトリプルパンチに見舞われる住宅価格。
建材インフレだけでなく、性能向上義務や申請手数料の大幅なコストUPによって、
注文住宅が手の届かない所に行ってしまうことでしょう。
市民が注文で住宅を建てられた時代の終焉です。
元々、オーダーメイドは高価なのが当たり前。
その方だけの間取り、その方だけの仕様で、すべて一品モノで作る注文住宅。
安く造ってきたのは、性能が無かったからです。
見た目の部分だけをオーダーに合わせて造っていたから出来たこと。
長持ち・暖かさ・頑丈、と言った大事な部分なおざりになっていただけのこと。
そこがいよいよ必要になり、義務化になったわけです。

サンキハウスの提案
サンキハウスはセミオーダーをお勧めします。
間取りの自由度は残しながらも、性能はトップレベル、
頑丈さは耐震等級3、長持ちは長期優良住宅取得ですが、
価格は税込み、2000万円台をキープします。
長持ちする住宅は、50年後も使える家とも言えます。
再販価格を期待するなら、流行りのデザイン、独特な間取りはマイナスにしかなりません。
新発売のラ・クープで間取り3Dシミュレーションをしてみませんか。☘️
https://diyhome.co.jp/lacoupe/
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆

新築注文住宅
【羨望のブリティッシュハウス】
UA値=0.35 C値=0.3
憧れの英国風の家。車の多い道沿いでも家の中はとても静か

新築注文住宅
【和のツーバイシックス住宅】
UA値=0.34 C値=0.3
暖かさと換気にこだわり、和の家をツーバイシックス工法で実現

リノベーション
【生まれ変わった築22年の家】
UA値=1.43 → 0.55
中古住宅をリノベしたら、吹き抜けのある明るく暖かい家に!
2025年03月09日
室内の乾燥と冬の雨
まだ暫く加湿器をそのままにして下さい。
雨が降っていると乾燥も緩和すると思ってしまいますが、
気温が低い日の雨が家の中の湿度を改善することはありません。
3月に入ってからの気象庁による「日ごとの気温と湿度」の表によると、

気象庁:過去の気象データ
3月6日の静岡市は「雲のち小雨」という天気でした。
気温は割と高く、最高15.2℃(平均10.5℃)、平均湿度71%でした。
室内の湿度は40%以上をキープしたいと思い、
外気をそのまま取り入れると、乾燥が進みます。
(冬の乾燥について東大の前准教授の解説は → こちら)
空気は温度によって含める水蒸気量が変化するので、
気温の低い日の水蒸気量は、雨が降っていても少ないのです。
それでは、
3月6日の温度10.5℃(平均)、湿度71%(平均)の外気を
換気のため室内に取込んだ場合の水蒸気量を見ると、

気温10.5℃、相対湿度71%の空気の絶対湿度は5.56g/kgDA
この空気が室内(22℃)に取り込まれた時、暖房によって次第に22℃になって行くのですが、
温度が上昇しても絶対湿度(g)は変わらず、相対湿度(%)が下がっていきます。

気温22℃、相対湿度34.1%の空気の絶対湿度は5.56g/kgDA
要するに、上図の赤点は右に移動するだけです。
曲線で表されているのが相対湿度のメモリですが、70%の曲線上にいたものが、
30%と40%の間に移動します。
ですから換気を多めに行って、雨の湿度を部屋取り入れようとしても、
逆に室内の相対湿度が下がることになるのです。
エアコン暖房が過乾燥の原因という誤解があります。
パネルヒーターでもコタツでも部屋の温度が高くなれば、相対湿度は下がります。
昔のガスや石油ストーブなど燃焼系の暖房器具は、
燃料を燃やした時に水蒸気が出て加湿になるのですが、
酸素を消費し空気を汚すので換気量を増すことになり、ムダが多くなります。
【結論】
冬、室内が乾燥するのは換気のせいです。
外の湿度が室内の湿度を決めています。
換気システムを全熱式の一種熱交換にすれば、
乾燥した外気を直接室内に入れる事がなくなります。
湿度も交換できるので冬の過乾燥も軽減できます。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
★冬季限定★『床下エアコン体験会』inモデルハウス
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地~キッチン中心のワンルームLDKの家
開放感とプライバシーを両立~太陽の軌道に合わせたパッシブな家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の漆喰平屋の家
大好きなカフェの居心地を叶えた高性能住宅
明るさ優先!2階リビングの家で、明るく開放的な暮らし
空間と木質感がいっぱい~家事ラクで高性能な家
アーチ開口とパイン材がたくさん!北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2025年03月02日
4月の改正で2×4住宅はどうなる?
弊社のメインである2×4工法の2階建ての住宅にどの様な影響があるのでしょうか?
2025年4月 建築基準法改正の主な変更点
| 改正項目 | 概要 |
|---|---|
| 4号特例の縮小 | 小規模建築物に対する構造審査の特例(4号特例)が縮小され、木造2階建て住宅などが新たに審査対象となる。 |
| 構造規制の合理化 | 木造建築物の仕様や壁量基準が見直され、設計の柔軟性が向上する。 |
| 省エネ基準の適合義務化 | すべての新築建築物に対し、省エネ基準への適合が義務化される。 |
| 大規模木造建築物の防火規定変更 | 大規模な木造建築物に関する防火規定が見直され、木材利用の促進が図られる。 |
| 中層木造建築物の耐火性能基準の合理化 | 中層の木造建築物における耐火性能基準が合理化され、設計の自由度が高まる。 |
| 既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除 | 既存の不適格建築物に対し、現行基準の一部適用が免除される措置が導入される。 |
この中で新築住宅に関連するのは、①4号特例の縮小、②構造規制の合理化、③省エネ基準の適合義務化です。
2階建ての「4号」と言う建物(木造)がなくなり、特例が消滅します。
構造の検討(仕様規定の壁量計算)結果の提出と承認が必要になります。
(許容応力度による構造計算は従来と同様で、今回変更なし)
また、省エネ基準(義務)適合の根拠、エネルギー消費の数値化の提出です。
弊社2×4住宅における変更点
③省エネ基準の適合義務化に対しては、ZEH基準以上の高性能住宅を標準として来ましたので、
作業や提出物に変化はありません。
①4号特例の縮小と②構造規制の合理化については大きく変わります。
在来木造工法と2×4工法では違う部分もありますが、共通している所として、
従来、壁量計算には重い屋根、軽い屋根という2つの重さで構造を考察していたものを、
家の仕様や太陽光パネルの有無などの重さを個別に計算する方式に変わります。
事前に国土交通省の用意した表計算シートを使って、各々の住宅の仕様を入力し、
個別の数値(床面積に乗ずる数値)を出しておきます。
その床面積に乗ずる数値を壁量計算をする際に使用し壁量を求める方式になりました。
在来木造の場合はこれに加え、一本一本の柱が支える面積から小径(柱の太さ)の確認計算が加わりました。
2×4工法は壁で支える工法なので、柱の太さに対する確認はありません。
現在打合せ中のお客様で実際どの様な変化があるのか試してみました。

「床面積に乗ずる数値」表計算シート
表の下の方にあるオレンジ枠にある6つ数値を転記して使います。 等級3の1階が54、2階が30と言う数値です。
実際、以前と大して違いませんでした。(今まで積雪30㎝を自主的?に加算していましたので😅)☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
★冬季限定★『床下エアコン体験会』inモデルハウス
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地~キッチン中心のワンルームLDKの家
開放感とプライバシーを両立~太陽の軌道に合わせたパッシブな家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の漆喰平屋の家
大好きなカフェの居心地を叶えた高性能住宅
明るさ優先!2階リビングの家で、明るく開放的な暮らし
空間と木質感がいっぱい~家事ラクで高性能な家
アーチ開口とパイン材がたくさん!北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2025年02月16日
4月からJAS材が貴重になる?
「4号建築物の廃止と特例の縮小」によって構造審査が変わり、
提出書類が増えたり審査期間が長くなって混乱すると言われています。
また、省エネ基準の義務化も始まり、全ての住宅に外皮(断熱)計算と一次エネルギー消費量も求められ、
それにも手間取るでしょう。
確かにそれも問題ですが、
今回の構造審査の中身を見るとより大きな影響がありそうなのが、JAS材だと思います。
JASとはなにか?
JASは日本農林規格のことで、飲食料品、農産物、林産物、畜産物、水産物などの品質や成分、生産方法、管理方法、サービスなどの基準を農林水産大臣が定める国家規格です。
国が認めた登録認証機関から認証を受けると、その証しとして日本農林規格を満たす製品や広告等にJASマークを表示することができます。
木材のJASは製材や集成材、合板などの建築材料を格付けし、強度認証された製品にスタンプされる仕組みです。
しかし日本国内で流通している、特に製材はこのJAS認証を受けていない、いわゆる無等級材が大半なのです。

出展:林野庁
上の表の製材の行で、格付率が13%となっていますね。
他の行、特に集成材やCLTは90%程ですから、製材が突出して少ないです。
これは何を意味するのかと言うと、
現在、在来軸組工法で使われている木材は無等級材が大半であるが、4月からの法改正では格付のない木材は
強度計算で不利になるため、使われなくなるのではないか。
その為、JASの格付のある製材に需要が集中するのではないかと考えています。
強度計算が厳格になる理由は、
最近の窓の重量化(ペアやトリプルガラスが増えて)や太陽光発電パネルの設置などで、
建物の重さが増していますが、それを考慮せず建てている現状があります。
構造計算(許容応力度)を行っている場合は、建物の重さを設計重量として考慮しますが、
壁量計算の場合は、いわゆる「重い屋根と軽い屋根」しか重さを考慮する部分がありませんでした。
しかし、4月以降は厳密に建物の重さを考慮して、それを支える柱の小径を決めることが必須になります。
その際、柱材の強度が必要なのですが、無等級材の場合は一律で強度が低い数値になっているため、
JASの格付けのある柱材が重宝されると考えられます。
ちなみに、2×4材は100%でJAS格付を取っていますので、
13%はその2×4材を含んでの数ですから在来軸組工法の木材だけですと、数字はより小さいと思われます。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
★冬季限定★『床下エアコン体験会』inモデルハウス
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地~キッチン中心のワンルームLDKの家
開放感とプライバシーを両立~太陽の軌道に合わせたパッシブな家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の漆喰平屋の家
大好きなカフェの居心地を叶えた高性能住宅
明るさ優先!2階リビングの家で、明るく開放的な暮らし
空間と木質感がいっぱい~家事ラクで高性能な家
アーチ開口とパイン材がたくさん!北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2025年02月09日
世界は間に合うのか?
日本は宣言にほぼ沿った内容で推移していますが、
家庭と業務部門の建物に関するエネルギー消費が目標値を超えていました。
そこで今回は世界ではどうなっているのか?を考えて行きます。
前回提示したグラフで解るように、日本のCO2排出量は世界6位です。
では他の5か国と共に過去からの推移を見ましょう。

上位6か国(EUは加盟国全体)で世界全体の68%を占めていて、日本は全体の3%。
中国の排出量が突出していて全体の32%です。
最近の異常気象は地球温暖化の影響であることは世界の常識と思いますが、
この状況を改善するため生まれたのが国連気候変動枠組条約(UNFCCC)です。
今までのこの会議の主な成果と内容を見てみましょう。
国連気候変動枠組条約の主な成果
| 年 | 会議名 / 取り組み | 主な成果・内容 |
|---|---|---|
| 1992年 | 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)採択 | 気候変動対策の国際的枠組みを設定。地球温暖化の抑制を目的とする。 |
| 1997年 | 京都議定書(COP3) | 先進国に対し、2008~2012年の間に温室効果ガス排出量を1990年比で平均5.2%削減する義務を設定。 |
| 2009年 | コペンハーゲン合意(COP15) | すべての国が自主的な排出削減目標を提出することを求める。1.5~2℃の気温上昇抑制目標を設定。 |
| 2015年 | パリ協定(COP21) | すべての国が参加する法的拘束力のある合意。気温上昇を2℃未満(1.5℃目標)に抑えることを決定。各国が自主的削減目標(NDC)を設定し、5年ごとの更新(GST)。 |
| 2021年 | グラスゴー気候合意(COP26) | 石炭火力発電の「削減」に合意。各国の排出削減目標(NDC)の強化(5年ごとより頻繁に)を要請。 |
| 2022年 | シャルム・エル・シェイク合意(COP27) | 「損失と損害」基金の設立決定(気候変動による被害を受ける発展途上国を支援)。 |
| 2023年 | ドバイ合意(COP28) | 初のグローバル・ストックテイク(GST)を実施。化石燃料削減の国際的な合意を促進。 |
この中で重要なのは、COP21のパリ協定で決まった5年ごとの評価(GST)です。
そして、COP28で初めてGSTを実施しました。
その結果は2025年2月までに各国が結果を表明することになっていて、
2025年11月のCOP30で今後の取組みを更新・強化する予定です。
さて、問題は米国です。
トランプ大統領が就任し、早々にパリ協定から離脱。
しかし、バイデン前大統領が昨年12月の任期中、
米国の排出削減目標(NDC)を国連に提出しているのです。
この結果は早々に周知されることになります。
2025年のCOP30では米国抜きでの開催になりますが、
結果は世界に公表され、米国内にも影響を及ぼすと思われます。
そして次は中国です。
世界全体の3分の1強のCO2を排出していて、なお増え続けています。
米国が離脱した今、習近平総書記は世界に対して意地を見せるかも知れません。
劇的にCO2排出量を減らすことができるかも。中国の体制なら可能かもと思ってしまいます。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
★冬季限定★『床下エアコン体験会』inモデルハウス
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地~キッチン中心のワンルームLDKの家
開放感とプライバシーを両立~太陽の軌道に合わせたパッシブな家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の漆喰平屋の家
大好きなカフェの居心地を叶えた高性能住宅
明るさ優先!2階リビングの家で、明るく開放的な暮らし
空間と木質感がいっぱい~家事ラクで高性能な家
アーチ開口とパイン材がたくさん!北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2025年02月01日
あと5年、間に合うのか?
地球温暖化対策のため2050年カーボンニュートラルを宣言している日本は、
その途中の2030年にマイルストーンとして「2013年度比46%削減」を謳っています。
2025年現在、いったいどこにいるのか。
そもそも2013年度比46%削減は可能なのか。
地球全体の話なので、日本だけ達成しても意味ないし、
アメリカの大統領をみていると不安になりますが、
日本人としてはきっちりやり遂げたいとも思いますよね。
地球における日本の影響度は?

各国が排出するCO2の比較(2021年)
中国が31.8%でワースト1位、アメリカが13.6%で2位
以下、EU7.7% 、インド6.8%、ロシア5.0%と続き、
日本が6番目で3.0%です。
日本の中の現在地は?

出展:環境省2021年
少し古い情報ですが、最も最近のデータでは、
業務と家庭部門がオントラックでないようです。
ただ、全体としては何とか可能性がある状態です。

出展:経産省2021
赤い破線で示しているのが途中の削減目標水準で、
若干上に突き抜けているものの、まだ挽回の余地ありです。
では、家庭と業務部門の中身を見てみましょう。
共に建物などの建築物に関わるCO2排出であり、
日本の建物の断熱不足や消費サイクルの速さ(短命)が災いとなっている様です。
家庭部門と業務部門の違い
| 項目 | 家庭部門 | 業務部門 |
|---|---|---|
| 対象 | 一般家庭(個人の住居) | 商業施設・オフィス・公共施設・工場の事務部門 |
| 主なエネルギー使用 | 照明、冷暖房、給湯、調理、家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機など) | 照明、空調、給湯、業務用機器(パソコン・プリンター・コピー機など) |
| 主なCO2排出源 | 電力消費、ガス・灯油の使用 | 電力消費、大規模空調・給湯システム |
| 削減対策の例 | 高効率家電の導入、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の推進、太陽光発電の普及 | 省エネ建築(ZEB: ゼロ・エネルギー・ビル)の推進、高効率空調・LED照明の導入、エネルギーマネジメントシステムの活用 |
| 省エネ基準の違い | 住宅用の省エネ基準(断熱性能や設備効率の規定) | 建築物省エネ法に基づく規制・誘導基準(大規模施設では省エネ計画の届出が必要) |
では、家庭部門を担っているサンキハウスとして取り組むべきは、
今までと変わりません。
新築住宅なら、超高気密・高断熱のG2.5(断熱等級6.5)高性能住宅で、
ZEH以上(これからはGX志向型住宅)を標準とします。
ただ、インフレで資材や労務費が高騰し、建物価格が上昇して行く。
賃金上昇がインフレに追いついて行かないので新築住宅が厳しい。
それゆえ、中古住宅の断熱リフォームや性能向上リノベーションが大事になると思います。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2025年01月21日
160万円補助金、GX志向型住宅ってなに?
「GX志向型住宅」という新たなヤツが登場しました。
160万円補助金と言ったほうが有名かも知れません。
GXって何?
グリーン・トランスフォーメーションの略称だそうです。
志向型って、どういう意味?
これから、これを目指すと言うことでしょうか。
要件は3点
①断熱等性能等級6以上 UA値=0.46(6,7地域)
②再エネを除く一次エネ消費量の削減率35%以上
③再エネ含む一次エネ消費量の削減率100%以上
子育て世帯などの他要件はなく、シンプルな条件の補助金になってます。
GX志向型住宅と長期優良住宅の補助金の比較
| 項目 | GX志向型住宅 | 長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 断熱等性能等級 | 断熱等級6以上 | 断熱等級5以上 |
| 一次エネルギー消費量削減率 | 再エネを除き35%以上削減 | 再エネを除き20%以上削減 |
| 再生可能エネルギー導入後の一次エネルギー収支 | 100%以上削減(正味ゼロ) | 100%以上削減(正味ゼロ) |
| 補助金額 | 最大160万円 | 最大80万円(建替えの場合100万円) |
| 対象者 | すべての世帯 | 子育て世帯等 |
①断熱等性能等級6以上はもう説明の必要はないと思いますが、
HEAT20のG2以上の外皮性能が必要です。
③再エネ含む一次エネ消費量に削減率100%以上は今までのZEHと同じです。
屋根に載せる太陽光発電でその家での消費エネルギー(家電を除く)を賄えれば良いです。
問題は②再エネを除く一次エネ消費量に削減率35%以上ですね。
削減率35%以上って、どこで確認すれば良いのでしょう?

BELSを取っているなら、評価書を見ると分かります。
「再エネなし」の削減率を見て下さい。 この例では39%です。
③再エネ含む100%以上もこの例では137%です。
(※赤丸で囲んだ数値参照)
どんな性能の住宅がGX志向型住宅になるか?ですが、
在来工法木造の場合は、105㎜厚の壁の充填断熱だけでは難しそうです。
付加断熱が必要になると思います。
2×4工法の場合は、2×6(140m㎜)の外壁の充填断熱なら
断熱等級6+位のUA値(0.4前後)になるので、外壁2×6にすれば取れます。
最近、新発売のサンキハウスの規格住宅「ラ・クープ」(LaCoupe)ならGX志向型住宅になります。
お値打ち価格の「ラ・クープ」は、160万円補助金も標準仕様でゲットできます。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年12月22日
建売りと注文住宅の中間なら

2025年4月から、省エネ住宅の義務化が始まるのをご存じですか?
断熱等級4という水準に義務化されるのですが、
この断熱等級4は、1999年に「次世代省エネ基準」と言われていた古い水準です。
そう、25年経ってようやく義務化されることになったのですが、
この水準、今となっては余りにも低すぎる。
色々な住宅関係団体(HEAT20 、新住協など)で
性能が足りないと言われていて、今ではその上に3段階も上位水準があるのです。
ですから、いま義務化(断熱等級4)水準の家を建ててもすぐ陳腐化してしまいます。
これから家を建てるなら断熱等級6以上を目指すのが良いでしょう。
ところがこの断熱等級6は結構大変な水準で、
在来工法では付加断熱が必須となるためコストアップが避けられません。
160万円補助金(GX志向型住宅)はその断熱等級6が条件になっている他に、
一次エネルギー消費量を35%以上削減すると言う条件も付いていて、これがかなりハードルが高いです。
断熱等級6をギリギリクリアではチョット難しいのが現状です。
断熱等級6+とか断熱等級6.5とか言われている所まで断熱性能を上げなければならないでしょう。
いずれにしても、コストがかかる話です。
そこで、LaCoupe(ラクープ)を開発しました。
2x6工法を採用し壁厚が+5㎝あるので、断熱材が1.5倍ほど厚く充填されています。
自由設計ですと、間取りもゼロから考える為コストがかかりますが、セミオーダーなのでコストを抑えることができます。
でも建売りとは違い、ご自身で間取りを作る自由度のあるセミオーダー住宅なので、
家づくりの楽しさを味わっていただけると思います。
こちらに→詳しい専用ページがありますので、ぜひご覧ください。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年12月15日
2×4住宅でも、和の設えで…
在来工法の様に柱や梁を見せることはできません。
2×4工法には、
鉄骨やRCと同じ耐火構造として認めるかわりに、
木の部分を全て被覆しなければならないルールがあるからです。
(だから、火災保険料が鉄骨なみに安い。)
その為、「和」を好む方々からは少し残念と言われることもあります。
構造材である木を「被覆して燃えない」を優先している2×4住宅ですが、
内装の設え(しつらえ)で和に見せることはできます。
今回はその様な事例を紹介します。

琉球畳とシラス壁の色合いが和を醸し出しています。

格子の建具があるとグッと和を強調します。
色の使い方が大事です。
ハッキリした色ではなく、くすんだ色と言うか和色というか、自然由来の色がいいと思います。
木もヒノキや杉など明るい色の木で、
節のない正目がそれらしいです。


低い造作棚と丸い照明が和を演出。

しっくい壁も和を表現するアイテムの一つですね。
今年建てた新築住宅からの画像ですが如何ですか。
どちらも見学会を行っておりませんので、初お目見えです。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年12月08日
寒くなる前に仕上げました
日本海エリアでは雪も降り始めて、本格的な冬の到来だ!
そこで、寒波が来る前にお風呂を暖かくするリフォームが二つ。
一つはこちら、

「とにかくお風呂が寒くて冷たくて、すぐ冷えちゃう。」と、ご不満のN様。
そこで、昔ながらの風呂をユニットバスにリフォーム。
でも単にユニットバスに交換するだけではダメです。
直ぐに冷たくなるのは、「気流止め」がないため。
過去のブログ記事はこちら→「風呂リフォームはここが大事」

LIXILのユニットバスリフォームのイメージ図
そう、このお家も床下を流れる空気を止めて、基礎断熱にしました。
二つ目はこちら

古い造作お風呂だけど、ユニットバスにするのは大変。
そこで、特に寒かったガラスからの冷輻射熱を「ハニカムサーモスクリーン」で防ぎました。
窓もマドリモに交換

こちらの浴室の寒さ対策は以上ですが、
このお宅、太陽光発電の昼間の電気が余っているので、
ボイラーをリンナイのEcoOne(エコワン)に替えました。
これはエコキュート(電気)とエコジョーズ(ガス)が合体したハイブリッド給湯機です。
湯切れの心配なしにお湯をガンガン使えるけど、省エネNO1!というガスをあまり消費しない給湯機なので、
ガス会社さんが売りたくない🤣ガス器具なのです。

今なら補助金15万円がもらえます。😁☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年11月30日
日本の窓、ドイツの窓
気密性や断熱性のことはまったく考えていない、夏を旨とする窓であります。
視界を遮ること、また通風の為の窓として少し前まで広く使われていました。
隙間風が入ってくるため、夏は良くても、冬は特に浴室に使われている場合、
過酷な環境になります。

帯状のガラスがルーバーの様に斜めに重なって閉まりますが、隙間が完全には塞がれません。
ガラスも一枚なので、ガラスを通して冷たさも伝わります。
冬を迎える前に、カバー工法(マドリモ)で樹脂製の上げ下げ窓に交換しました。

一回り小さな窓になってしまいましたが、これで冷気から解放されます。
ドイツ発祥の窓にドレーキップ窓と言うのがあります。
「ドレ―」が内開き、「キップ」が内倒しを示す単語だそうですが、
ヨーロッパでは一般的な窓で、すべてをこのドレーキップ窓にすることもあるそう。

内倒し(換気モード)の状態
このほかに内開きにもなるので、お掃除が簡単なのも特徴です。

取っ手を捻ってロックするのですが、パッキンが潰れて気密性はバッチリ。
隙間はまったくありません。
今では日本の窓メーカーさんも作っているので、日本でも手に入ります。
ルーバー窓とドレーキップ窓、どちらも換気機能のある窓ですが、
日本とドイツではまったく違った製品になっています。
日本人はどこまで我慢強いのでしょうか?
特に浴室にあるルーバー窓は交換しましょう。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年11月24日
小屋裏エアコンの壁内湿度ご報告【マニアック】
「今日の33℃、64%の空気は危険」で試した、
室内側に付加した断熱材の効果をお知らせします。
簡単にこの実験の主旨をご説明します。
(1)小屋裏壁内は気温33℃、相対湿度64%の外気
(湿度は簡単に壁内に侵入するので防ぎようはない。この外気の露点温度は25.3℃)
(2)室内の温度が25℃になるように冷房する
(3)小屋裏部屋の温度が20~23℃に達する
(4)室内側に断熱材を足して、壁面の温度を露点温度以上に上げたいがはたして

小屋裏壁内の1年間の温湿度グラフ
上記グラフから読み取れること
(1)30㎜のネオマを室内側に付加し、温度が3℃上昇
(2)設置後も3℃の上昇では壁内結露は解消せず
(3)壁内結露は10月初旬の最高気温30℃を下回った頃に解消
(4)断熱材の厚み70㎜で温度が5℃上昇する計算になるが非現実的
日本の夏が、今年の様に異常な高温・高湿度が常態化するなら、
壁内結露は普段の冷房で日常的に起こっているかも知れません。

タイベックスマートによる防湿・気密層
特に局所的な冷房をするなら、透湿性の在る壁で、
室内側に湿度を逃がす対策が必要でしょう。
(でもこれで室内の湿度は下がり辛くなる。
なぜか? 外気の湿度が常に室内に侵入するからです。)
湿度対策は冬より夏の方が難しくなって来ています。
夏の外気が気温33℃、相対湿度63%を超えると25℃が露点温度になるので、
冷房温度を控えめ(27℃位)に設定して戴くのが安全です。
しかし、27℃が涼しいのかと言うと、湿度が高いままだと涼しく感じられません。
これからは、湿度コントロールが大事なのかもしれませんね。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年11月17日
床下エアコン、様々な取付高
そうなると床下エアコン暖房の季節。
サンキハウスで床下エアコンを始めて11年目のシーズンになります。
さて、「床下エアコン」で検索すると色々な画像が表示されます。
数は少ないですが、床置きエアコンを使う事例もあります。

フィックスホーム様のHPから
この場合、吹き出し口が上下にあり、
上から吹出せば床上を暖める(冷やす)ことができます。
短所は、機器が高価なこと。
コストを考慮するなら普通の壁掛エアコンを使います。
普通の壁掛エアコンを設置する例では、

ダイシンビルド様のHPから
箱で囲って、風が床下に向くように設置しています。
メンテナンス性を優先した設置位置ですが、
吹出し口を真下に向けても、風は基礎の耐圧板に当たり、
遠くまで届かない欠点もありますね。
もう少し下に設置している例もあります。

アーキトリック様のHPから
この場合、なぜこの高さなのかは疑問の残る所です。
と言うのは、メンテナンスには低すぎてやり辛く、
けれども距離があって、温風も床下に届きにくいですね。
さらに下げて設置するタイプもあります。
壁掛エアコンの頭しか見えません。
サンキハウスはこの位置に設置しています。

サンキハウスの場合はこの高さです
メンテナンス用に床板が外れるようになっているのと、
横に点検口を設置してあり、機械の交換の際にも床下に潜れます。
色々な設置位置があるのは、未だ試行錯誤にある証拠。
全国で色々試しながら進化している状態なんですね。
11年目のシーズン、
床下エアコンは経験のあるサンキハウスにお任せください。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年11月10日
結露ですが、問題ありません
暖かくしてお過ごしください。
さて、10年ぶりくらいにあるOB様から質問をいただきました。
内容は朝、外に出て外壁を見ると結露が生じていて心配になったとの事。

朝露による結露ですが、ところどころ縦に筋状に表れていて、
何でかな?と言うご質問でした。
筋状の間隔は45㎝位なので、間柱の間隔と一致します。
考えられるのは、
間柱や2階床のある所は外壁材が木材に接近していて木材からの放射があり、
間柱や2階床のない(断熱材の入っている)所では温度差が大きいと考えられます。
その為、深夜の冷えこみで外壁材が冷えたところに、
朝方の湿った空気の流入と気温上昇で、冷えた外壁面に結露が現れました。
断熱材のある無しで温度差が生じ、結露が筋状に表れたものと考えられます。
チョット珍しい現象ですが、寒暖差の激しい季節に起こることがあります。
この季節は外に停めてある車も朝はビショビショになっていることがあり、
同様の現象が起こっていますよね。
温度差がなければ起きない現象なので、家の構造体には影響はありません。
なぜなら、外壁は二重の防水構造になっているため外壁の裏側が濡れても
構造体に水分は行きません。
また、構造体は室内からの熱伝導で結露するほど冷たくなりません。
結露は自然現象です。条件が整えば起こります。
原因は湿った空気と温度差。

上の写真、コップの内外の温度差が結露を生みます。
寒い冬の到来、家の中の暖かい湿った空気が窓ガラスで結露する季節です。
今回の外壁の結露は、外壁材より外気の方が暖かく湿っていたと言う事。
珍しい現象でしたね。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2024年10月27日
風呂リフォームはここが大事
今の新築はユニットバスが普及し、タイルと浴槽の造作風呂に比べ格段に暖かくなりました。
また、基礎断熱を採用するサンキハウスなら、

【基礎断熱】ユニットバスが入る廻りの基礎に断熱材を施工
ベタ基礎の内側に断熱材を張り付けているので構造体が断熱され、より暖かいです。
昔のタイルと浴槽のお風呂をリフォームするなら
「気流止め」をしなければ暖かいお風呂にすることはできません。
なぜか?
それは、昔のお風呂を解体すると出てくるのはむき出しの地面だからです。

【無断熱】昔のタイルと浴槽のお風呂の下は地面がむき出し
この様に昔の床下には断熱という考え方はなかったから仕方ないですね。
方法は二つ
①今の新築と同じように、基礎断熱にする。
②床下は通気構造のままで、気流止め+断熱浴槽を採用する。
①の基礎断熱にするが理想的ですが、やはり費用も相当掛かります。
そこで、②の気流止め+断熱浴槽を使うのが良いのではないでしょうか。
断熱浴槽はユニットバスを買うときに暖熱浴槽仕様にすれば終わり。
あとの気流止めが建築会社の腕の見せどころです。

床下は通気のまま、気流止めで壁への空気侵入を防ぐ
国の指針でも図入りで説明書がありました。
床下から壁に空気が侵入すると、ユニットバスが暖かく保てません。
それを行うのが気流止めと言われる措置です。
ただリフォームの場合、解体してみないと中がどうなっているかわかりません。
地域や年代によって様々な作り方があるので、対処方法のその時々で考えなければなりません。

【気流止め】壁を閉じて床下と壁を分離した
上の写真のお宅ではこの様に気流止めを施工しました。
これなら、床下からの空気が壁の中には入れませんね。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
一年中快適な住み心地の家と季節の便りを運ぶ庭
開放感とプライバシーを両立した、遊びゴコロ満載の家
工作好きな家族が快適に暮らす“G2.5”の平屋
大好きなカフェの居心地が叶う家
2階リビングのある家で、明るく開放的な暮らしを
高性能と家事ラクを叶えたジャパンディスタイルの家
住むほどに愛着を増していく「ときめきの家」
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家