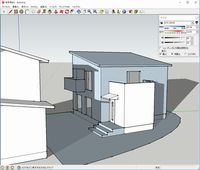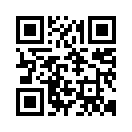2025年03月29日
2×4工法と許容応力度計算
2025年4月(あと2日です)から建築基準法が大きく変わります。
変わる所はいくつかあるのですが、中でも「4号特例の
縮小」が、当社メインである木造住宅に大きく拘わるので影響が大きいです。
屋根に載る太陽光パネルや窓ガラスの多重化による
重量増に対応するため、構造根拠の提出が必須になりました。
俗にいう構造計算が必要になると言われる所以です。
この構造計算ですが、許容応力度計算という手法が
一般的で、構造の先生にお願いして計算して戴く必要があります。
(自前でソフトウェアを買って計算することも出来ますがハードルが高い。)
ただ、今までの方法が無くなったわけではありません。
それは壁量計算と呼ばれるもので、品確法の耐震等級3を取得できます。
「品確法の」と付ける理由は、「許容応力度計算の」
耐震等級3と区別する為に構造塾さんなどが流行らせた言い方で、
国とすれば同じ耐震等級3で区別はないはずですが…。
その為「許容応力度計算の」耐震等級3のほうが上位にある印象になっています。
2×4(ツーバイフォー)工法は日本語で枠組壁工法と呼びます。
木質パネルの壁工法と言い換えると解りやすいかも知れません。

要は、パネルの組合わせで6面体を作り、6面体の組み合わせで建物を形作る工法です。
部材は標準化・規格化されていて一つ一つの部材の強度も明確になっています。
また、配置バランスや開口部の上限などもルール化され、力の伝達・構造解析が容易です。
ですから、必要な量の壁を適切な位置に配置することで高耐震の建物になります。
必要な量の壁を適切な位置に配置=壁量計算なのです。
2×4工法と壁量計算は相性が良いのです。
今回の建築基準法改正では壁量計算もより厳格になり、
個々の建物の大きさ重さや積載荷重も含めた全体の重量を考慮し、壁量を求める方法に変わりました。
この改正に合わせて、
2×4工法の計算ソフト「らくわくVer2」もリリースされ
早速使ってみた所、使い勝手も良く、結果にも大きな変化がありませんでした。

改正後もスムーズに仕事ができると確認できました。
改正点は主に3つ
1.壁量計算のため床面積に乗ずる数値を邸別に代入
2.壁倍率をmax5倍から7倍に
3.垂れ壁や腰壁も条件により準耐力壁として計上可能
(らくわくは壁量計算で間取りを解析しますが、個々の梁や基礎構造は許容応力度計算を行っております。)
一方、在来工法は無数の部材を自由に使える為、
その部材の組み合わせで作られた建物がどの程度の強さか?には解析が必須です。
その為「許容応力度計算」が必要になります。☘️
変わる所はいくつかあるのですが、中でも「4号特例の
縮小」が、当社メインである木造住宅に大きく拘わるので影響が大きいです。
屋根に載る太陽光パネルや窓ガラスの多重化による
重量増に対応するため、構造根拠の提出が必須になりました。
俗にいう構造計算が必要になると言われる所以です。
この構造計算ですが、許容応力度計算という手法が
一般的で、構造の先生にお願いして計算して戴く必要があります。
(自前でソフトウェアを買って計算することも出来ますがハードルが高い。)
2×4工法と壁量計算は相性が良い
ただ、今までの方法が無くなったわけではありません。
それは壁量計算と呼ばれるもので、品確法の耐震等級3を取得できます。
「品確法の」と付ける理由は、「許容応力度計算の」
耐震等級3と区別する為に構造塾さんなどが流行らせた言い方で、
国とすれば同じ耐震等級3で区別はないはずですが…。
その為「許容応力度計算の」耐震等級3のほうが上位にある印象になっています。
2×4(ツーバイフォー)工法は日本語で枠組壁工法と呼びます。
木質パネルの壁工法と言い換えると解りやすいかも知れません。

要は、パネルの組合わせで6面体を作り、6面体の組み合わせで建物を形作る工法です。
部材は標準化・規格化されていて一つ一つの部材の強度も明確になっています。
また、配置バランスや開口部の上限などもルール化され、力の伝達・構造解析が容易です。
ですから、必要な量の壁を適切な位置に配置することで高耐震の建物になります。
必要な量の壁を適切な位置に配置=壁量計算なのです。
2×4工法と壁量計算は相性が良いのです。
今回の建築基準法改正では壁量計算もより厳格になり、
個々の建物の大きさ重さや積載荷重も含めた全体の重量を考慮し、壁量を求める方法に変わりました。
この改正に合わせて、
2×4工法の計算ソフト「らくわくVer2」もリリースされ
早速使ってみた所、使い勝手も良く、結果にも大きな変化がありませんでした。

改正後もスムーズに仕事ができると確認できました。
改正点は主に3つ
1.壁量計算のため床面積に乗ずる数値を邸別に代入
2.壁倍率をmax5倍から7倍に
3.垂れ壁や腰壁も条件により準耐力壁として計上可能
(らくわくは壁量計算で間取りを解析しますが、個々の梁や基礎構造は許容応力度計算を行っております。)
一方、在来工法は無数の部材を自由に使える為、
その部材の組み合わせで作られた建物がどの程度の強さか?には解析が必須です。
その為「許容応力度計算」が必要になります。☘️
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
Posted by sanki at 17:39│Comments(0)
│つぶやき