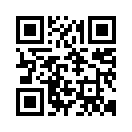2023年05月14日
結露は冬だけの現象ではない
今週は「劣化対策について考える第3弾」として夏型結露について考えます。
夏型結露のメカニズムについてはこちらをご覧ください。→「冬の結露と夏の結露」
5~6月は気温も湿度も適度な状態ですので、窓を開けて外気を取り込むには絶好の季節です。
しかし6月中旬以降は梅雨が始まり外気は高湿度になるので、窓開け換気は好ましくありません。
建物の床下は梅雨時期に大変高湿度になっており、多くの住宅でカビが発生していますが、
床下の点検など行っていない為、気づいていない事が多いです。
床下以外の屋内に外の湿気を入れることはエアコン冷房の電気代としてマイナスですし、
冷気により断熱の弱い部分や温度の低い部分に結露が発生してしまうこともあります。
古民家など昔の作りの建物なら隙間風も多く断熱材も使われていない為、湿気を貯め込まず、
通風で涼を得ることが建物の維持にもなっていましたが、今の住宅にはその方法は適しません。
気密化した現代の住宅は出来るだけ外気の湿度を避け、エアコン冷房による除湿を活用し、
室内の湿度を低く保つことが重要です。
必要以上の換気を行うことは外の無尽蔵な湿気を室内に取り込んでしまうと肝に銘じて、
健康のための必要十分な空気以外は室内に入れない様にしましょう。
弊社の建てる住宅には床下エアコンを設備した家が多いので、床下エアコン暖房を使った
除湿の裏技を紹介します。

「夏なのに暖房」と驚かれるのも無理はありませんが、
床下は室内よりも温度が若干低いため、夏型の結露を起こすことも多い場所です。
そこで、25~26℃で暖房運転をすると床下の温度を上げる事が出来ますし、
上階のエアコン(小屋裏エアコンやホールエアコンなど)で冷房をすると家全体として
再熱除湿運転として機能するという仕組みです。
少し電気代が掛かりますが、カラッとした低湿度で、しかも寒くない適温が可能です。
体に優しい湿度と温度は建物にも優しい環境なのです。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
夏型結露のメカニズムについてはこちらをご覧ください。→「冬の結露と夏の結露」
5~6月は気温も湿度も適度な状態ですので、窓を開けて外気を取り込むには絶好の季節です。
しかし6月中旬以降は梅雨が始まり外気は高湿度になるので、窓開け換気は好ましくありません。
建物の床下は梅雨時期に大変高湿度になっており、多くの住宅でカビが発生していますが、
床下の点検など行っていない為、気づいていない事が多いです。
床下以外の屋内に外の湿気を入れることはエアコン冷房の電気代としてマイナスですし、
冷気により断熱の弱い部分や温度の低い部分に結露が発生してしまうこともあります。
古民家など昔の作りの建物なら隙間風も多く断熱材も使われていない為、湿気を貯め込まず、
通風で涼を得ることが建物の維持にもなっていましたが、今の住宅にはその方法は適しません。
気密化した現代の住宅は出来るだけ外気の湿度を避け、エアコン冷房による除湿を活用し、
室内の湿度を低く保つことが重要です。
必要以上の換気を行うことは外の無尽蔵な湿気を室内に取り込んでしまうと肝に銘じて、
健康のための必要十分な空気以外は室内に入れない様にしましょう。
弊社の建てる住宅には床下エアコンを設備した家が多いので、床下エアコン暖房を使った
除湿の裏技を紹介します。

「夏なのに暖房」と驚かれるのも無理はありませんが、
床下は室内よりも温度が若干低いため、夏型の結露を起こすことも多い場所です。
そこで、25~26℃で暖房運転をすると床下の温度を上げる事が出来ますし、
上階のエアコン(小屋裏エアコンやホールエアコンなど)で冷房をすると家全体として
再熱除湿運転として機能するという仕組みです。
少し電気代が掛かりますが、カラッとした低湿度で、しかも寒くない適温が可能です。
体に優しい湿度と温度は建物にも優しい環境なのです。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2023年05月14日
劣化対策について考える②
住宅を90年持たせるには、部材の取り換えやすさが大事だと前の記事で書きました。
理由は90年持つ外装建材は存在しないので、90年のどこかで交換する必要があるからです。
「瓦屋根なら90年持つんじゃない。」
瓦は持つかも知れませんが、それを支える下地(野地板)はどうでしょう。
野地板は雨にも結露水にもさらされる(可能性がある)重要な建材だと知ってましたか?

雨水の防水は分かりますが、結露水は気が付かない方も多いので、説明します。
室内の空気には多くの水蒸気が含まれています。
料理やお風呂、燃焼型の暖房機器、発汗・呼気からも水蒸気は発生します。
(冬季の過乾燥を嫌った過加湿も大きな問題です。)
水蒸気は室内を上昇し、やがて屋根(天井)の断熱材に到達します。
その時、水蒸気をせき止める気密シートを張っておくか、断熱材が含んだ湿気を除去する仕組みがないと、
冬の夜、屋根が冷えて屋根下地(野地板)の裏側で結露を起こします。

上からの防水、下からの水蒸気による結露水に侵されることがあると、屋根下地(野地板)を交換しなければなりません。
ここで、壁は2重構造にするのに屋根は2重構造を施さないのかと言う疑問が沸きます。
そうです。屋根下地(野地板)も2重にしてあげれば、
上の野地板は防水専用
下の野地板は結露専用と考えることができ、対策を施し易くなります。
弊社のモデルハウスでは、この考え方の元、2重屋根構造にしました。
上の野地板と下の野地板の間は通気層を取ります。
そうする事で、屋根の内側に溜まった湿気を外に排出する事が出来ます。

2重屋根構造はまた、夏の暑さ対策としても有効なので、夏は暑さ対策、冬は結露対策になり
野地板の交換を行わなくても90年持つ構造になると考えています。
費用が掛かる工法なので、今だ実績は2棟ですが、これからは増えて来ることでしょう。😁
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
理由は90年持つ外装建材は存在しないので、90年のどこかで交換する必要があるからです。
「瓦屋根なら90年持つんじゃない。」
瓦は持つかも知れませんが、それを支える下地(野地板)はどうでしょう。
野地板は雨にも結露水にもさらされる(可能性がある)重要な建材だと知ってましたか?

雨水の防水は分かりますが、結露水は気が付かない方も多いので、説明します。
室内の空気には多くの水蒸気が含まれています。
料理やお風呂、燃焼型の暖房機器、発汗・呼気からも水蒸気は発生します。
(冬季の過乾燥を嫌った過加湿も大きな問題です。)
水蒸気は室内を上昇し、やがて屋根(天井)の断熱材に到達します。
その時、水蒸気をせき止める気密シートを張っておくか、断熱材が含んだ湿気を除去する仕組みがないと、
冬の夜、屋根が冷えて屋根下地(野地板)の裏側で結露を起こします。

上からの防水、下からの水蒸気による結露水に侵されることがあると、屋根下地(野地板)を交換しなければなりません。
ここで、壁は2重構造にするのに屋根は2重構造を施さないのかと言う疑問が沸きます。
そうです。屋根下地(野地板)も2重にしてあげれば、
上の野地板は防水専用
下の野地板は結露専用と考えることができ、対策を施し易くなります。
弊社のモデルハウスでは、この考え方の元、2重屋根構造にしました。
上の野地板と下の野地板の間は通気層を取ります。
そうする事で、屋根の内側に溜まった湿気を外に排出する事が出来ます。

2重屋根構造はまた、夏の暑さ対策としても有効なので、夏は暑さ対策、冬は結露対策になり
野地板の交換を行わなくても90年持つ構造になると考えています。
費用が掛かる工法なので、今だ実績は2棟ですが、これからは増えて来ることでしょう。😁
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2023年04月30日
90年保つ家について考える
他の誰かも書いていましたが、世間ではチャットGPTの話題で持ち切りですね。
だいぶ前になりますが、第2次AIブームの時に米国の大学の工学大学院に在籍してたことがあり、
AIについての学習もしていました。
まだコンピューターパワーの乏しい時代でしたので、ニューラルネットワークや機械学習などの
実装がなく、エキスパートシステム(推論エンジン)どまりでした。
その後の2010年頃、機械学習の一種であるディープラーニングが登場し飛躍的に進歩しました。
そのAI技術が一般にも公開されたため、世界は動揺しています。
シンギュラリティが現実のものとなるかも知れません。🤖
2009年6月に施行された「長期優良住宅」認定制度の中に、劣化対策等級3があります。
これは、住宅の構造体が「3世代(75~90年)持つための対策が行われていること」とし、
その為の部材や工法および維持管理を行うことで認定されます。
しかし、一発で90年持つ部材も工法もありませんので、計画的に点検し、修理や交換を行う事が必要です。
そしてその為には、交換しやすい工法や部材を使う事も重要な要素です。
維持管理しやすくするために日本の住宅の課題は何か?
以前も書いた内容ですが、日本のサッシ(窓)のツバ問題があります。→ 以前のブログ記事
日本のサッシには取付容易性・防水性を高めるために、窓枠にツバが付いています。

出典:新潟 住まい「緑の家」天然・自然素材と超高断熱高気密
この為、窓を取り換えるには窓の廻りの外壁を大きく切り取らなければなりません。

この様に外壁を一部切り取りサッシを外す必要があります。
手間がかかりますし、外壁を復旧しなければなりません。
30年で建て替えを前提にしてきた日本の住宅業界は今変化の時にいます。😁
【あとがき】
生成系AIに「劣化対策等級3のイメージ図を描いて」とお願いしたら、絵が出て来ました。

意味はありませんが、イメージは伝わるかな?
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
だいぶ前になりますが、第2次AIブームの時に米国の大学の工学大学院に在籍してたことがあり、
AIについての学習もしていました。
まだコンピューターパワーの乏しい時代でしたので、ニューラルネットワークや機械学習などの
実装がなく、エキスパートシステム(推論エンジン)どまりでした。
その後の2010年頃、機械学習の一種であるディープラーニングが登場し飛躍的に進歩しました。
そのAI技術が一般にも公開されたため、世界は動揺しています。
シンギュラリティが現実のものとなるかも知れません。🤖
2009年6月に施行された「長期優良住宅」認定制度の中に、劣化対策等級3があります。
これは、住宅の構造体が「3世代(75~90年)持つための対策が行われていること」とし、
その為の部材や工法および維持管理を行うことで認定されます。
しかし、一発で90年持つ部材も工法もありませんので、計画的に点検し、修理や交換を行う事が必要です。
そしてその為には、交換しやすい工法や部材を使う事も重要な要素です。
維持管理しやすくするために日本の住宅の課題は何か?
以前も書いた内容ですが、日本のサッシ(窓)のツバ問題があります。→ 以前のブログ記事
日本のサッシには取付容易性・防水性を高めるために、窓枠にツバが付いています。

出典:新潟 住まい「緑の家」天然・自然素材と超高断熱高気密
この為、窓を取り換えるには窓の廻りの外壁を大きく切り取らなければなりません。

この様に外壁を一部切り取りサッシを外す必要があります。
手間がかかりますし、外壁を復旧しなければなりません。
30年で建て替えを前提にしてきた日本の住宅業界は今変化の時にいます。😁
【あとがき】
生成系AIに「劣化対策等級3のイメージ図を描いて」とお願いしたら、絵が出て来ました。

意味はありませんが、イメージは伝わるかな?
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2023年04月09日
小屋裏エアコンと湿度【冬】
近頃、「小屋裏エアコン」で弊社のHPに行き着く人が増えています。
まだ暑くもないのになぜ「小屋裏エアコン」で検索されるのか?
疑問ですが、それならと今回は小屋裏エアコン関連の話をしてみます。😁
昨年の夏、7月初旬~10月初旬までの3ヶ月間、小屋裏エアコン冷房を稼働。
その時の考察として書いた記事(1年目小屋裏エアコンの結果【マニアック】)
その続きとして、冬の間の小屋裏の壁内と屋根内の湿度状況を報告します。

全館冷房用エアコンのある小屋裏には、壁と屋根(天井)に温湿度計を設置してあり、
年間を通して断熱層の温湿度を計測しています。
下の図はその計測データです。(左:壁内、右:屋根内)

昨年の夏の屋外の湿度は相当なものでした。
2022年7月平均気温が26.1℃、平均相対湿度が79% → 露点温度22.2℃
2022年8月平均気温が27.4℃、平均相対湿度が76% → 露点温度22.8℃
小屋裏エアコンは小屋裏部屋をチャンバーとして使い、そこから直接各部屋に冷気を送ります。
ダクトレス方式なので、送風用のファンもなく、ダクト内の清掃も必要ありません。
下階の温度を27℃にするため、小屋裏部屋の温度は20~21℃位になります。
ですから、外気が小屋裏部屋の温度に触れると露点(結露する温度)に達してしまいます。
その為、7月後半~9月中旬にかけて結露を起こしています。(上図の赤〇を参照)
住宅の壁と屋根には合板が張られているので、直接断熱材が外気に触れているわけでありません。
それでも、外気に含まれる水蒸気は何の抵抗もなく合板を通り抜け、断熱材に到達します。
[caption id="attachment_21099" align="alignnone" width="475"] 水蒸気の粒子は水の粒子の1000万分の2の大きさ[/caption]
水蒸気の粒子は水の粒子の1000万分の2の大きさ[/caption]
水蒸気の粒子は大変に小さく、木材などは侵入を防げません。
この結果は、勿論ホームズ君の定常結露計算を使い分かっていた事です。
しかし、瞬間的(と言っても2か月近くあるが)な結露なら、それほど心配いらないかも。
とも思い、年間を通して壁内と屋根内の断熱層の状態を観察しています。
図の下の方にある青色の線が2023年2月に記録した相対湿度の最低値になります。
23%程度まで湿度が下がり、からっからと言える乾燥状態です。
今年もこのまま7月には小屋裏エアコン冷房を運転するつもりです。
昨年と同じような湿潤状態になるのか?、少し期間が減少するのか?など
観察を続けて行きたいと思います。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
まだ暑くもないのになぜ「小屋裏エアコン」で検索されるのか?
疑問ですが、それならと今回は小屋裏エアコン関連の話をしてみます。😁
昨年の夏、7月初旬~10月初旬までの3ヶ月間、小屋裏エアコン冷房を稼働。
その時の考察として書いた記事(1年目小屋裏エアコンの結果【マニアック】)
その続きとして、冬の間の小屋裏の壁内と屋根内の湿度状況を報告します。

全館冷房用エアコンのある小屋裏には、壁と屋根(天井)に温湿度計を設置してあり、
年間を通して断熱層の温湿度を計測しています。
下の図はその計測データです。(左:壁内、右:屋根内)

昨年の夏の屋外の湿度は相当なものでした。
2022年7月平均気温が26.1℃、平均相対湿度が79% → 露点温度22.2℃
2022年8月平均気温が27.4℃、平均相対湿度が76% → 露点温度22.8℃
小屋裏エアコンは小屋裏部屋をチャンバーとして使い、そこから直接各部屋に冷気を送ります。
ダクトレス方式なので、送風用のファンもなく、ダクト内の清掃も必要ありません。
下階の温度を27℃にするため、小屋裏部屋の温度は20~21℃位になります。
ですから、外気が小屋裏部屋の温度に触れると露点(結露する温度)に達してしまいます。
その為、7月後半~9月中旬にかけて結露を起こしています。(上図の赤〇を参照)
住宅の壁と屋根には合板が張られているので、直接断熱材が外気に触れているわけでありません。
それでも、外気に含まれる水蒸気は何の抵抗もなく合板を通り抜け、断熱材に到達します。
[caption id="attachment_21099" align="alignnone" width="475"]
 水蒸気の粒子は水の粒子の1000万分の2の大きさ[/caption]
水蒸気の粒子は水の粒子の1000万分の2の大きさ[/caption]水蒸気の粒子は大変に小さく、木材などは侵入を防げません。
この結果は、勿論ホームズ君の定常結露計算を使い分かっていた事です。
しかし、瞬間的(と言っても2か月近くあるが)な結露なら、それほど心配いらないかも。
とも思い、年間を通して壁内と屋根内の断熱層の状態を観察しています。
図の下の方にある青色の線が2023年2月に記録した相対湿度の最低値になります。
23%程度まで湿度が下がり、からっからと言える乾燥状態です。
今年もこのまま7月には小屋裏エアコン冷房を運転するつもりです。
昨年と同じような湿潤状態になるのか?、少し期間が減少するのか?など
観察を続けて行きたいと思います。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2023年03月12日
ツーバイフォーのすすめ
コロナ禍も3年が過ぎ、ようやく終息の兆しが出てきました。
5月のゴールデンウィーク明けには、感染症法の5類に移行する事も決まりました。
コロナ禍中に住宅業界で大変流行った現象があります。
それは、住宅ブロガーの躍進です。
色々な専門家が出てきた中で、私も大変参考にさせて戴いた建築ブロガーに構造塾があります。
こちらの先生ですね。

久しぶりに過去の動画を覗いてみました。
今も新しい動画を発信中ですが、表示回数の多いのは過去のモノです。当たり前か!
「やっぱり、簡潔に分かりやすい説明でためになるよね。」
とか
「ちょっとしゃべり方が独特で面白い。」
とか、感じながら見ていると、「おや!」と思う解説に出くわしました。
以前に何度も見た動画ですが、その時には気が付かなかった内容です。
https://www.youtube.com/watch?v=_0HNVLMtk3Q

【マニアック】な内容なので、悪しからず、
在来工法も2×4工法も壁で建物を支えます。
(在来は柱だよっていう人がいるかも知れませんが、
筋交いなしでは成り立ちませんので、やはり壁で支えます。)
壁には釘や合板の有無で壁倍率の違いがそれぞれありますが、
同じ倍率(動画では倍率2と言ってます)で比べた場合、
2×4工法の壁の方が在来工法の壁より強いと言ってます。
(17分20秒~あたりで喋っている内容をご覧ください。)
同じ長さの壁があった場合、2×4工法の壁の方が耐力がある。
どれほどの差があるのかは言っていませんが、強さが違うと
言ってますね。
耐震等級3はそれぞれの等級1の1.5倍の強さ(壁量)があるのだから、
2×4工法の耐震等級3は在来工法のそれより強いと言えるって事ですな。
これから大いに使わせて戴きます。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
New! 3/18(sat)・19(sun)『コンパクトだけど「欲しい」を全部叶えたお家』完成見学会
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
5月のゴールデンウィーク明けには、感染症法の5類に移行する事も決まりました。
コロナ禍中に住宅業界で大変流行った現象があります。
それは、住宅ブロガーの躍進です。
色々な専門家が出てきた中で、私も大変参考にさせて戴いた建築ブロガーに構造塾があります。
こちらの先生ですね。

久しぶりに過去の動画を覗いてみました。
今も新しい動画を発信中ですが、表示回数の多いのは過去のモノです。当たり前か!
「やっぱり、簡潔に分かりやすい説明でためになるよね。」
とか
「ちょっとしゃべり方が独特で面白い。」
とか、感じながら見ていると、「おや!」と思う解説に出くわしました。
以前に何度も見た動画ですが、その時には気が付かなかった内容です。
https://www.youtube.com/watch?v=_0HNVLMtk3Q

【マニアック】な内容なので、悪しからず、
在来工法も2×4工法も壁で建物を支えます。
(在来は柱だよっていう人がいるかも知れませんが、
筋交いなしでは成り立ちませんので、やはり壁で支えます。)
壁には釘や合板の有無で壁倍率の違いがそれぞれありますが、
同じ倍率(動画では倍率2と言ってます)で比べた場合、
2×4工法の壁の方が在来工法の壁より強いと言ってます。
(17分20秒~あたりで喋っている内容をご覧ください。)
同じ長さの壁があった場合、2×4工法の壁の方が耐力がある。
どれほどの差があるのかは言っていませんが、強さが違うと
言ってますね。
耐震等級3はそれぞれの等級1の1.5倍の強さ(壁量)があるのだから、
2×4工法の耐震等級3は在来工法のそれより強いと言えるって事ですな。
これから大いに使わせて戴きます。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
New! 3/18(sat)・19(sun)『コンパクトだけど「欲しい」を全部叶えたお家』完成見学会
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
タグ :耐震等級3
2023年02月26日
耐震性を上げる外壁なら、これ一択【マニアック】
外壁の種類によって耐震性に違いがあるのか? 考えてみましょう。
一般的に、軽い外壁なら耐震性に貢献すると思います。
振り子現象を思い出して下さい。

屋根の場合、頭が重いと振り子の頭が左右に大きく振れてしまい、
建物の揺れが大きくなるため、耐震性の低下につながります。
同じように外壁が重ければ同様の性質と言えますね。
そこから考えると、ガルバリウムの外壁材は軽いので、耐震性向上に
なると言えるかも知れません。
ただし、上に行くに従って段々重さが影響するとは思いますが、
外壁は下にも張りますので、屋根ほど影響は大きくないと考えられます。
では次の考え方として、壁の面剛性はどうでしょう?
2×4工法の建物が地震に強いのは、構造用合板によって面剛性を高めた結果です。

さてここからがチョット難しいのですが、お付き合いください。
上の図の面材は下地壁です。
下地壁とは、外壁の内部に隠れてしまう合板を張った壁の事ですが、
この様なモノです。↓

この写真は室内側から見たものですが、この面材の外側にタイベック
(透湿防水シート)を張って、胴縁を付けて、外壁材を張るのですが、
その外壁材が今回のテーマです。
外壁は2重の壁(構造用面材と外壁材)になります。
【長期優良住宅では必須】

↑印のある所に通気層があり、外の空気が流れる
さて、ここまでご理解いただけると、この先が今回の結論になります。
外壁は外観上の見た目(意匠)として大事な部材ですが、
耐震としての機能も持たせる事が出来れば一石※三鳥になります。
※ 三鳥とは、意匠・家の劣化防止・耐震です
軽い外壁の代名詞であるガルバリウム鋼板はどうでしょうか。
薄い鋼板(0.3㎜)なので面材としての剛性は期待できませんね。
次に、引っ掛けサイデイングはどうでしょう。

金具で外壁材を引っ掛けてるだけなのでこれも耐震性は期待できません。
(地震の際、多くのサイデイング板が金具から外れてしまう様です。)
では最後に、くぎ打ちサイディングを見てみましょう。

専用の釘で直接サイディング板を胴縁に打ち付けていきます。
これなら、下地の構造用合板と共に一体の壁になって耐震強度も増します。
サイディング板を金具で引っ掛ける様になったのは、
くぎ打ちによる穴から雨水が染み込み外壁が汚れたり、
穴が広がってヒビが入ったりして意匠的に好ましくないからです。
耐震的には劣っても、今はメンテナンスの少ない金具引っ掛け方式が主流です。
でも、その心配(雨水の染み込みやヒビ割れ)がなかったらどうですか?
弊社の推奨する「サイデイング下地の塗り壁仕上げ」を見てみましょう。

専用の下地サイデイング(無柄・無塗装板)を釘打ちで※りゃんこ張りします。
※ りゃんこ張りとは、千鳥張りのことで接合部が一直線にならない

板の長さは3m。これをりゃんこ(千鳥)に張ってあります。
下地のサイディング張りができました。
普通の釘打ちサイディング外壁ならこれで終わりですが、弊社推奨の
「サイデイング下地の塗り壁仕上げ」外壁はここからが違います。

まず、サイデイングの角をメッシュテープで補強します。

その上から樹脂製メッシュを全面に張り、板と板を一体化します。

メッシュが隠れるまで下地モルタルを塗り込み、下地完成。
どうでしょう。
釘の頭も穴もすべて樹脂メッシュとモルタルでカバーされ
雨水はおろか、空気の出入りもありません。
外壁全体が一体となっていますので、サイディング同士の衝突もなく、
地震の揺れを壁面全体で受け止めます。
最後は、お好きな材質、色の仕上げ材を塗って終了です。


国産の漆喰を塗ってみました。いかがですか。
「サイデイング下地の塗り壁仕上げ」外壁は窓廻りの
コーキングもすべて塗り壁材によって上からカバーされます。
従って、コーキングの劣化も起こらず、メンテナンス性も抜群。
【この工法の最も優れた特徴かも知れません】
直塗りの塗り壁とは全く違う、優れた外壁システムなのです。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
一般的に、軽い外壁なら耐震性に貢献すると思います。
振り子現象を思い出して下さい。

屋根の場合、頭が重いと振り子の頭が左右に大きく振れてしまい、
建物の揺れが大きくなるため、耐震性の低下につながります。
同じように外壁が重ければ同様の性質と言えますね。
そこから考えると、ガルバリウムの外壁材は軽いので、耐震性向上に
なると言えるかも知れません。
ただし、上に行くに従って段々重さが影響するとは思いますが、
外壁は下にも張りますので、屋根ほど影響は大きくないと考えられます。
では次の考え方として、壁の面剛性はどうでしょう?
2×4工法の建物が地震に強いのは、構造用合板によって面剛性を高めた結果です。

さてここからがチョット難しいのですが、お付き合いください。
上の図の面材は下地壁です。
下地壁とは、外壁の内部に隠れてしまう合板を張った壁の事ですが、
この様なモノです。↓

この写真は室内側から見たものですが、この面材の外側にタイベック
(透湿防水シート)を張って、胴縁を付けて、外壁材を張るのですが、
その外壁材が今回のテーマです。
外壁は2重の壁(構造用面材と外壁材)になります。
【長期優良住宅では必須】

↑印のある所に通気層があり、外の空気が流れる
さて、ここまでご理解いただけると、この先が今回の結論になります。
外壁は外観上の見た目(意匠)として大事な部材ですが、
耐震としての機能も持たせる事が出来れば一石※三鳥になります。
※ 三鳥とは、意匠・家の劣化防止・耐震です
軽い外壁の代名詞であるガルバリウム鋼板はどうでしょうか。
薄い鋼板(0.3㎜)なので面材としての剛性は期待できませんね。
次に、引っ掛けサイデイングはどうでしょう。

金具で外壁材を引っ掛けてるだけなのでこれも耐震性は期待できません。
(地震の際、多くのサイデイング板が金具から外れてしまう様です。)
では最後に、くぎ打ちサイディングを見てみましょう。

専用の釘で直接サイディング板を胴縁に打ち付けていきます。
これなら、下地の構造用合板と共に一体の壁になって耐震強度も増します。
サイディング板を金具で引っ掛ける様になったのは、
くぎ打ちによる穴から雨水が染み込み外壁が汚れたり、
穴が広がってヒビが入ったりして意匠的に好ましくないからです。
耐震的には劣っても、今はメンテナンスの少ない金具引っ掛け方式が主流です。
でも、その心配(雨水の染み込みやヒビ割れ)がなかったらどうですか?
弊社の推奨する「サイデイング下地の塗り壁仕上げ」を見てみましょう。

専用の下地サイデイング(無柄・無塗装板)を釘打ちで※りゃんこ張りします。
※ りゃんこ張りとは、千鳥張りのことで接合部が一直線にならない

板の長さは3m。これをりゃんこ(千鳥)に張ってあります。
下地のサイディング張りができました。
普通の釘打ちサイディング外壁ならこれで終わりですが、弊社推奨の
「サイデイング下地の塗り壁仕上げ」外壁はここからが違います。

まず、サイデイングの角をメッシュテープで補強します。

その上から樹脂製メッシュを全面に張り、板と板を一体化します。

メッシュが隠れるまで下地モルタルを塗り込み、下地完成。
どうでしょう。
釘の頭も穴もすべて樹脂メッシュとモルタルでカバーされ
雨水はおろか、空気の出入りもありません。
外壁全体が一体となっていますので、サイディング同士の衝突もなく、
地震の揺れを壁面全体で受け止めます。
最後は、お好きな材質、色の仕上げ材を塗って終了です。


国産の漆喰を塗ってみました。いかがですか。
「サイデイング下地の塗り壁仕上げ」外壁は窓廻りの
コーキングもすべて塗り壁材によって上からカバーされます。
従って、コーキングの劣化も起こらず、メンテナンス性も抜群。
【この工法の最も優れた特徴かも知れません】
直塗りの塗り壁とは全く違う、優れた外壁システムなのです。☘️
▲▼▲▼▲ お知らせ ▲▼▲▼▲
現在、お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年10月30日
1年目小屋裏エアコンの結果【マニアック】
もうすぐ聖一色モデルハウスを建てて1年が経ちます。
このモデルハウスでは新たな取組として、小屋裏エアコン冷房に挑戦しました。
小屋裏エアコン冷房は床下エアコン暖房とは違い内部結露の危険があり難しい。
その事は以前のブログで説明をしておりますが、ひと夏を過ごした考察を行います。
まず、どの様に内部結露が起こるのか、簡単に説明します。
外の湿気が合板を通り越して壁内(屋根内)に入り込みます。 室内が冷房で
冷やされている場合、内装材越しに壁内(屋根内)が冷やされて内部結露する。
というメカニズムです。(詳しくはブログで説明していますので御覧下さい。)
小屋裏エアコン冷房では、小屋裏で作られた冷気を小屋裏空間を使って2階の
各部屋に分配する仕組みです。
そのため小屋裏部屋を冷房チャンバーとして20℃位に冷やすのですが、
その温度が壁内(屋根内)に伝わると結露を起こす露点温度以下なのです。
そこで、屋根を二重構造にして温度が伝わりにくくする対策を講じました。
結果としては、効果はあるが、完璧ではないという結論になりました。
現在施工中の小屋裏エアコンを装備しているMZ邸では、透湿気密シートを
小屋裏部屋の壁・屋根面に張り、余分な湿度は室内側に透湿させて拡散する
方法を取ることにしました。

安全に越したことはないので、お客様にはこの方法を提案しますが、
結露の量はわずかであり、屋根内にいたっては、時々露点を脱している事が分かりました。

左が壁内、右が屋根内(屋根内は露点が継続していない。)
聖一色モデルハウスはこの様に微量の結露が起こる状態なのですが、
実験として、数年継続観察してみようと思います。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在ご案内できるイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
このモデルハウスでは新たな取組として、小屋裏エアコン冷房に挑戦しました。
小屋裏エアコン冷房は床下エアコン暖房とは違い内部結露の危険があり難しい。
その事は以前のブログで説明をしておりますが、ひと夏を過ごした考察を行います。
まず、どの様に内部結露が起こるのか、簡単に説明します。
外の湿気が合板を通り越して壁内(屋根内)に入り込みます。 室内が冷房で
冷やされている場合、内装材越しに壁内(屋根内)が冷やされて内部結露する。
というメカニズムです。(詳しくはブログで説明していますので御覧下さい。)
小屋裏エアコン冷房では、小屋裏で作られた冷気を小屋裏空間を使って2階の
各部屋に分配する仕組みです。
そのため小屋裏部屋を冷房チャンバーとして20℃位に冷やすのですが、
その温度が壁内(屋根内)に伝わると結露を起こす露点温度以下なのです。
そこで、屋根を二重構造にして温度が伝わりにくくする対策を講じました。
結果としては、効果はあるが、完璧ではないという結論になりました。
現在施工中の小屋裏エアコンを装備しているMZ邸では、透湿気密シートを
小屋裏部屋の壁・屋根面に張り、余分な湿度は室内側に透湿させて拡散する
方法を取ることにしました。

安全に越したことはないので、お客様にはこの方法を提案しますが、
結露の量はわずかであり、屋根内にいたっては、時々露点を脱している事が分かりました。

左が壁内、右が屋根内(屋根内は露点が継続していない。)
聖一色モデルハウスはこの様に微量の結露が起こる状態なのですが、
実験として、数年継続観察してみようと思います。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在ご案内できるイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
タグ :小屋裏エアコン
2022年09月04日
エアコン選定と気密の関係
朝晩は少し暑さが和らぎ、夏がようやく終わりに近づいて来ていると感じます。
10日ほどで梅雨が終わり、7月始めから夏が始まった2022年ですが、
先週、気象庁は今年の梅雨明け宣言が間違っていたと発表。
2022年の梅雨は概ね例年と同じ長さの梅雨期間だったとしました。
「何だかなぁ~」と思うと共に、今年の夏は色々あったので、暑さと共に
この重苦しい空気を吹き飛ばして貰いたいものですね。🥺
🥮 🥮 🥮 🥮 🥮
先週の「冷房用エアコンの選定は難しい」の続編で、気密との関連について
書いてみたいと思います。
まずは、QPEXで計算できる換気の熱損失が大きな割合を占めているので、
説明します。

赤枠で囲った部分が、換気での熱損失で24.918W/Kになっています。
この住宅では、熱交換率70%の第1種熱交換換気システムを使っているので、
普通の家の3種換気よりも大幅に熱損失が少ないのですが、
それでも表の一つ上の開口部全体の熱損失(23.157W/K)より少し多い数値になっています。
(家中の窓から失われる熱より、換気で失われる熱の方が多い)
換気で失われる熱はかなり多いことがお分かり頂けたかと思います。
また、この家のUA値は0.34とかなりの高スペック(G2とG3の間くらい)です。
ここで問題なのは、UA値には換気による熱損失は加味されていませんので、
多くの住宅系YouTuberの方が指摘している通り、UA値を競っても意味がありません。
最終的にお施主様の望みは、①家中が暖かい(涼しい)こと、
②その実現の為の高熱費が出来るだけ少ない事、ですので、
換気も含めた家全体の熱損失を計算したQ値と暖冷房エネルギーを明示する事が大事なのです。
そして「気密」との関係ですが、
そもそも気密が良くない住宅では、この計算自体が成り立ちません。
家のあらゆる場所からの漏気(隙間風)があり、熱損失を計算してもその通りにはならず、
家は計算通りに冷えないし(暖まらない)、計算通りの光熱費にもなりません。
従って、計算した冷房(暖房)エネルギーで機種選定する事に意味はないので、
部屋の大きさに合わせた従来の方法でエアコンサイズを決めるしかないのです。
もちろん、家中を一台のエアコンで冷房(暖房)することは出来ません。
一見、マニアックな記事と思われるかもしれませんが、
家は本来マニアックな物理で成り立っているものであり、
マニアックな理論の無い住宅はただの高級なテント(笑)です。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
9/17(土)・18(日) 『2×6のお家 公開気密測定&構造見学会』
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
10日ほどで梅雨が終わり、7月始めから夏が始まった2022年ですが、
先週、気象庁は今年の梅雨明け宣言が間違っていたと発表。
2022年の梅雨は概ね例年と同じ長さの梅雨期間だったとしました。
「何だかなぁ~」と思うと共に、今年の夏は色々あったので、暑さと共に
この重苦しい空気を吹き飛ばして貰いたいものですね。🥺
🥮 🥮 🥮 🥮 🥮
先週の「冷房用エアコンの選定は難しい」の続編で、気密との関連について
書いてみたいと思います。
まずは、QPEXで計算できる換気の熱損失が大きな割合を占めているので、
説明します。

赤枠で囲った部分が、換気での熱損失で24.918W/Kになっています。
この住宅では、熱交換率70%の第1種熱交換換気システムを使っているので、
普通の家の3種換気よりも大幅に熱損失が少ないのですが、
それでも表の一つ上の開口部全体の熱損失(23.157W/K)より少し多い数値になっています。
(家中の窓から失われる熱より、換気で失われる熱の方が多い)
換気で失われる熱はかなり多いことがお分かり頂けたかと思います。
また、この家のUA値は0.34とかなりの高スペック(G2とG3の間くらい)です。
ここで問題なのは、UA値には換気による熱損失は加味されていませんので、
多くの住宅系YouTuberの方が指摘している通り、UA値を競っても意味がありません。
最終的にお施主様の望みは、①家中が暖かい(涼しい)こと、
②その実現の為の高熱費が出来るだけ少ない事、ですので、
換気も含めた家全体の熱損失を計算したQ値と暖冷房エネルギーを明示する事が大事なのです。
そして「気密」との関係ですが、
そもそも気密が良くない住宅では、この計算自体が成り立ちません。
家のあらゆる場所からの漏気(隙間風)があり、熱損失を計算してもその通りにはならず、
家は計算通りに冷えないし(暖まらない)、計算通りの光熱費にもなりません。
従って、計算した冷房(暖房)エネルギーで機種選定する事に意味はないので、
部屋の大きさに合わせた従来の方法でエアコンサイズを決めるしかないのです。
もちろん、家中を一台のエアコンで冷房(暖房)することは出来ません。
一見、マニアックな記事と思われるかもしれませんが、
家は本来マニアックな物理で成り立っているものであり、
マニアックな理論の無い住宅はただの高級なテント(笑)です。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
9/17(土)・18(日) 『2×6のお家 公開気密測定&構造見学会』
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年08月28日
冷房用エアコンの選定はムズイ
今年の夏は長くて暑いですね。
エアコン冷房がなければ生きていけない今日この頃ですが、
冷房用エアコンの機種選定は思いの他難しいのです。
(間違っても〜畳用というカタログ表示を信じるなかれ)
暖房用エアコンの機種選定に比べて、冷房用のそれが難しのは、
(1)家での生活・活動が全てエアコン冷房のマイナス要因となる
(2)省エネという視点では冷房能力の大が小を兼ねない
を考慮する必要があるからです。
(1)の「エアコン冷房のマイナス要因」とは、人体発熱、家電発熱、
料理、入浴、日射など、冬のエアコン暖房では全てが余裕(プラス)側に
働くアクティビティを熱源として見なさなければなりません。
(2)の「大は小を兼ねない」とは、大きな出力が出る機器でも、通常の
運転がその最大能力の30%も使っていない場合がほとんどで、効率の面で
考えるとより小さなモーターを70%位の出力で運転した方が高効率と
言われているからです。
そこで計算によって最適な冷房用エアコンを選びたいのですが、
その計算に必要な数値がQ値です。
今やUA値に取って代わられた感のあるQ値ですが、Q値にあってUA値にない
ものがあり、それ故Q値が必要になるのですが、新住協の温熱計算ソフトQPEX
で計算してみました。

赤枠の中に「住宅全体 141.78(W/K)」とありますね、これがQ値です。
Q値にあってUA値にないものとは、換気によるエネルギー損失です。
このQ値は、1℃室内温度を下げるのに必要なエネルギーそのもの、
故に、以下の式で必要な冷房エネルギー量を計算することができます。
冷房用エアコンの選定の方が暖房のそれより、考慮する要素が多いこと、
お分かりいただけましたか?
新住協のQPEXをつかえば、Q値計算と共に冷暖房機器の必要エネルギー計算も
行ってくれるので、大変重宝しています。

これで「2499.8W」つまり2.5KWの冷房エネルギーが必要な事が分かったので、
いくらかの余裕をもたせつつ、機種の選定を行おうと思います。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
エアコン冷房がなければ生きていけない今日この頃ですが、
冷房用エアコンの機種選定は思いの他難しいのです。
(間違っても〜畳用というカタログ表示を信じるなかれ)
暖房用エアコンの機種選定に比べて、冷房用のそれが難しのは、
(1)家での生活・活動が全てエアコン冷房のマイナス要因となる
(2)省エネという視点では冷房能力の大が小を兼ねない
を考慮する必要があるからです。
(1)の「エアコン冷房のマイナス要因」とは、人体発熱、家電発熱、
料理、入浴、日射など、冬のエアコン暖房では全てが余裕(プラス)側に
働くアクティビティを熱源として見なさなければなりません。
(2)の「大は小を兼ねない」とは、大きな出力が出る機器でも、通常の
運転がその最大能力の30%も使っていない場合がほとんどで、効率の面で
考えるとより小さなモーターを70%位の出力で運転した方が高効率と
言われているからです。
そこで計算によって最適な冷房用エアコンを選びたいのですが、
その計算に必要な数値がQ値です。
今やUA値に取って代わられた感のあるQ値ですが、Q値にあってUA値にない
ものがあり、それ故Q値が必要になるのですが、新住協の温熱計算ソフトQPEX
で計算してみました。

赤枠の中に「住宅全体 141.78(W/K)」とありますね、これがQ値です。
Q値にあってUA値にないものとは、換気によるエネルギー損失です。
このQ値は、1℃室内温度を下げるのに必要なエネルギーそのもの、
故に、以下の式で必要な冷房エネルギー量を計算することができます。
必要エネルギー = 温度差 × Q値(住宅全体) + 室内発生熱 + 日射取得熱 + ※潜熱
※潜熱とは、水蒸気の形で潜伏している熱
冷房用エアコンの選定の方が暖房のそれより、考慮する要素が多いこと、
お分かりいただけましたか?
新住協のQPEXをつかえば、Q値計算と共に冷暖房機器の必要エネルギー計算も
行ってくれるので、大変重宝しています。

これで「2499.8W」つまり2.5KWの冷房エネルギーが必要な事が分かったので、
いくらかの余裕をもたせつつ、機種の選定を行おうと思います。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年08月06日
快適湿度を保つための4ヶ条
小屋裏エアコン冷房が上手く実現できたので、次なる課題は『湿度管理』です。
大型で高価な設備(ダイキンの「デシカ」)を使えば温度を下げずに除湿が可能ですが、
機械は必ず壊れるもの。
壊れた時の既存設備の撤去と買い替えに300万円超を考えると現実的ではありません。
普通の壁掛けエアコン1台〜2台で全館冷暖房を実現したように、既存の設備だけで
『快適湿度を保つ家』を考えてみます。
素人なのにプロより住宅技術に詳しい「さとるパパの住宅論」さんの記事でも
エアコン冷房を上手に使って除湿するのが効果的との事。
目標は、室温27℃で相対湿度50%です。
絶対湿度で12.9g/㎥になります。
これを実現するのはかなり難しそうです。
室温23.8℃で相対湿度60%が同じ絶対湿度で12.9g/㎥になりますが、
これでは室温が低くなりすぎ。 寒すぎて冬の布団が必要になります。
また、
夏型(逆転)結露の心配も出て来るので室温はそこまで下げたくありません。
直ぐに解答は出ないのですが、必要な事はわかっています。
(1)気密性能(0.2cm/㎡程度)
(2)高効率な全熱型第一種熱交換換気システム
(3)70%の出力で連続冷房運転するに必要十分なエアコン
(4)透湿しない壁(外気から室内への)構造
難しさの基本はここにあります。
(4)の透湿しない壁(外気から室内への)構造は夏型(逆転)結露への対策に
透湿性のある気密シートが使えない事を意味しています。

その点で今行っている実験が役に立つ事でしょう。
(3)の70%の出力で連続冷房運転するに必要十分なエアコンも選定が難しい。
大は小を兼ねないので、住宅プランに応じた必要冷房能力を計算してジャストサイズの
エアコンを選択しなければなりません。
最後は(2)の更なる高効率な全熱型第一種熱交換換気システムの出現ですが、
今は湿度回収率が60%程度の為、もう少し効率の良い全熱交換が待望されます。
前回のブログでも触れたように、窓開け換気は厳禁ですので、
お風呂の換気だけでなくキッチンの換気設備も循環型にする必要があるかもです。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
大型で高価な設備(ダイキンの「デシカ」)を使えば温度を下げずに除湿が可能ですが、
機械は必ず壊れるもの。
壊れた時の既存設備の撤去と買い替えに300万円超を考えると現実的ではありません。
普通の壁掛けエアコン1台〜2台で全館冷暖房を実現したように、既存の設備だけで
『快適湿度を保つ家』を考えてみます。
素人なのにプロより住宅技術に詳しい「さとるパパの住宅論」さんの記事でも
エアコン冷房を上手に使って除湿するのが効果的との事。
目標は、室温27℃で相対湿度50%です。
絶対湿度で12.9g/㎥になります。
これを実現するのはかなり難しそうです。
室温23.8℃で相対湿度60%が同じ絶対湿度で12.9g/㎥になりますが、
これでは室温が低くなりすぎ。 寒すぎて冬の布団が必要になります。
また、
夏型(逆転)結露の心配も出て来るので室温はそこまで下げたくありません。
直ぐに解答は出ないのですが、必要な事はわかっています。
(1)気密性能(0.2cm/㎡程度)
(2)高効率な全熱型第一種熱交換換気システム
(3)70%の出力で連続冷房運転するに必要十分なエアコン
(4)透湿しない壁(外気から室内への)構造
難しさの基本はここにあります。
(4)の透湿しない壁(外気から室内への)構造は夏型(逆転)結露への対策に
透湿性のある気密シートが使えない事を意味しています。

その点で今行っている実験が役に立つ事でしょう。
(3)の70%の出力で連続冷房運転するに必要十分なエアコンも選定が難しい。
大は小を兼ねないので、住宅プランに応じた必要冷房能力を計算してジャストサイズの
エアコンを選択しなければなりません。
最後は(2)の更なる高効率な全熱型第一種熱交換換気システムの出現ですが、
今は湿度回収率が60%程度の為、もう少し効率の良い全熱交換が待望されます。
前回のブログでも触れたように、窓開け換気は厳禁ですので、
お風呂の換気だけでなくキッチンの換気設備も循環型にする必要があるかもです。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
タグ :絶対湿度
2022年07月31日
計算すれば窓は開けないでしょう
今日は朝から(AM9:00)から気温29℃の相対湿度78%で蒸し暑い。
絶対湿度を計算するサイトで計算してみると、22.4g/㎥もありました。
絶対湿度とは1立米(㎥)の空気に含まれている水蒸気の重さ(量)でグラム(g)で表されます。
気温によって含まれる水蒸気量が変わる相対湿度(%)より絶対湿度の方が、
肌感覚で湿度を実感できることは住宅系YouTuberの松尾設計室さんも語っていますし、
私も同意します。😁

出典:松尾設計室YouTube動画から
5年前のブログ記事でも書いている様に、夏の外気には多量の水蒸気が潜伏しており、
その空気が室内に取り込まれ、エアコン冷房すると多量の結露水が発生します。
ですから、エアコン冷房をするなら窓は開けてはイケません。
換気も限りなく少なくしたい所ですので、全熱の熱交換換気がエアコン冷房には最適です。
ここで問題になるのがお風呂場の換気です。
まだまだ、窓開け換気している方がほとんどですが、お風呂場の換気で窓を開けると、
同様なことが起こりますので、サンキハウスでは【浴室に換気扇はいらない?】がお勧め。
増えています。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
8/6(土)・7(日) 『子育て家族のオンとオフを楽しむお家』完成見学会
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
絶対湿度を計算するサイトで計算してみると、22.4g/㎥もありました。
絶対湿度とは1立米(㎥)の空気に含まれている水蒸気の重さ(量)でグラム(g)で表されます。
気温によって含まれる水蒸気量が変わる相対湿度(%)より絶対湿度の方が、
肌感覚で湿度を実感できることは住宅系YouTuberの松尾設計室さんも語っていますし、
私も同意します。😁

出典:松尾設計室YouTube動画から
5年前のブログ記事でも書いている様に、夏の外気には多量の水蒸気が潜伏しており、
その空気が室内に取り込まれ、エアコン冷房すると多量の結露水が発生します。
ですから、エアコン冷房をするなら窓は開けてはイケません。
換気も限りなく少なくしたい所ですので、全熱の熱交換換気がエアコン冷房には最適です。
ここで問題になるのがお風呂場の換気です。
まだまだ、窓開け換気している方がほとんどですが、お風呂場の換気で窓を開けると、
同様なことが起こりますので、サンキハウスでは【浴室に換気扇はいらない?】がお勧め。
増えています。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
8/6(土)・7(日) 『子育て家族のオンとオフを楽しむお家』完成見学会
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年07月17日
小屋裏エアコンが難しいわけ
7月初めは連日の猛暑でしたが、今は一転連日の雨。本格的な梅雨となっています。
この為、外気の高温多湿がエアコンで冷やされた壁内に結露を起こす* 逆転結露を
心配しなければなりません。
* 逆転結露は夏型結露とも呼びこちらに解説があります---> 【冬の結露と夏の結露】
外気の湿度がそのまま壁内(断熱材の室内側)の湿度とイコールではありませんが、
外気の湿度の高まりが壁内にも(合板を通り抜けて)影響します。
室内の温度が25℃程度までであれば壁内(断熱材の室内側)の湿度は露点に届かず、
逆転結露を起こすことはありません。
しかし、小屋裏エアコンを設備した小屋裏の壁は違います。
下階に冷気を届けるため20℃程度の冷えた空気が充満するので、小屋裏の壁内は
かなり厳しい状態になります。
そのことを実証するため、聖一色モデルハウスでは今夏、実験を行っています。

「小屋裏エアコンが難しい」と言われる所以はここにあります。
戻り梅雨が始まった7月12日以降外気の湿度上昇と共に、
小屋裏の壁内の湿度も上昇しました。
全館冷房のエアコン設定温度は25℃で、小屋裏エアコン付近は20℃~25℃を
前後していますが、その間3,4回露点に達しているのが分かります。

瞬間的とは言え、結露するのは好ましくありません。
これは何か対策が必要な状態です。
今年はこのまま実験を続けますが、来年には可変性透湿気密シートを張り、
逆転結露を解消するかを追跡調査する事にします。
サンキハウスの小屋裏エアコンは「適温多風」方式です。
この言葉は【「家は、空調。」24時間全館冷房(除湿)by 一条工務店】ブログで
発見した言葉ですが、よく調べられていて参考にさせていただきました。
「適温多風」以外には「低温微風」があるとのことですが、「低温微風」はさらに
温度が低いので逆転結露はより深刻になります。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
この為、外気の高温多湿がエアコンで冷やされた壁内に結露を起こす* 逆転結露を
心配しなければなりません。
* 逆転結露は夏型結露とも呼びこちらに解説があります---> 【冬の結露と夏の結露】
外気の湿度がそのまま壁内(断熱材の室内側)の湿度とイコールではありませんが、
外気の湿度の高まりが壁内にも(合板を通り抜けて)影響します。
室内の温度が25℃程度までであれば壁内(断熱材の室内側)の湿度は露点に届かず、
逆転結露を起こすことはありません。
しかし、小屋裏エアコンを設備した小屋裏の壁は違います。
下階に冷気を届けるため20℃程度の冷えた空気が充満するので、小屋裏の壁内は
かなり厳しい状態になります。
そのことを実証するため、聖一色モデルハウスでは今夏、実験を行っています。

「小屋裏エアコンが難しい」と言われる所以はここにあります。
戻り梅雨が始まった7月12日以降外気の湿度上昇と共に、
小屋裏の壁内の湿度も上昇しました。
全館冷房のエアコン設定温度は25℃で、小屋裏エアコン付近は20℃~25℃を
前後していますが、その間3,4回露点に達しているのが分かります。

瞬間的とは言え、結露するのは好ましくありません。
これは何か対策が必要な状態です。
今年はこのまま実験を続けますが、来年には可変性透湿気密シートを張り、
逆転結露を解消するかを追跡調査する事にします。
サンキハウスの小屋裏エアコンは「適温多風」方式です。
この言葉は【「家は、空調。」24時間全館冷房(除湿)by 一条工務店】ブログで
発見した言葉ですが、よく調べられていて参考にさせていただきました。
「適温多風」以外には「低温微風」があるとのことですが、「低温微風」はさらに
温度が低いので逆転結露はより深刻になります。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年07月10日
小屋裏エアコンは難しい?
今年の梅雨明けは早かったと言うか、梅雨がほとんどなかったです。
6月後半に猛暑日が続き、7月に入ると曇りや雷雨の日があったり、
今は水蒸気が多くムシムシ感があり「戻り梅雨」などと言われています。
こんな日は、家中が快適になる小屋裏エアコンを稼働して家でのんびり
寛ぐのも悪くありません。





6月後半に聖一色モデルハウスの小屋裏エアコンを動かし始めました。
打合せやモデル見学など、頻繁に利用していますが、2階の各部屋も
設定温度(25℃)通りの室温で安定し、湿度も55%前後で快適です。
『小屋裏エアコンは難しい』で検索するとたくさんの記事が出て来ます。
内容は、
(1)冷気を各部屋に分配できない
(2)設定温度通りの温度にならない
(3)逆転結露が心配
などです。
理由として、床下エアコン暖房の様に幾つかの工夫(気密性能と基礎断熱、
それに床下の空気の流れを阻害する基礎の立上りレイアウト)で解決できない
自然現象の難しさがあるためです。
(1)冷気を各部屋に分配できない
ダクトと送風ファンを使って各部屋に冷気を分配する方法を取る場合、
ダクト内の汚れやカビが心配になります。
(2)設定温度通りの温度にならない
室温が設定温度になる前にエアコン本体のセンサーが働いてしまう。
或は、戻り(リターン)空気が取り込めず、場所により温度ムラが生じる。
(3)逆転結露が心配
気温30℃相対湿度80%の外気が壁や屋根の断熱材に侵入すると室温26℃で
露点に達してしまう計算になり、エアコンのある小屋裏の壁や屋根の中で
逆転結露を起こしてしまう。
(実際は、外気がそのまま壁や屋根内に侵入する訳ではなく、露点温度ももう少し低い温度と考えれるるが、
小屋裏を冷やさないと下階に冷気を届けられないので、出来れば20℃程度までは下げたい。)

上記の例では、壁の中の空気が28℃・相対湿度70%の場合、室温19℃以下で壁内の室内側が結露する。
特に(3)の逆転結露には注意を払わなければなりません。
弊社モデルハウスでは、通年での壁内・屋根内の温湿度を実測しており、
季節によって外気の影響がどの様に構造体、特に壁や屋根の内側に影響が
あるか調べています。

この様に小屋裏エアコンで全館冷房する場合、湿度と温度、冷気の届く距離に
難しさがあります。
この全てを解決するには、温度と湿度と流量(送風量)を適切にコントロール
しなければなりません。
その為の技術として、
(1)透湿性のある気密施工
(2)透湿性のある屋根防水と通気層
(3)外だし室温センサー
(4)流量(送風量)コントロール
がなければ、小屋裏エアコンを実現できないのです。
やっぱり、小屋裏エアコンは難しいですね。
でも、サンキハウスでは実現していますよ。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
6月後半に猛暑日が続き、7月に入ると曇りや雷雨の日があったり、
今は水蒸気が多くムシムシ感があり「戻り梅雨」などと言われています。
こんな日は、家中が快適になる小屋裏エアコンを稼働して家でのんびり
寛ぐのも悪くありません。





6月後半に聖一色モデルハウスの小屋裏エアコンを動かし始めました。
打合せやモデル見学など、頻繁に利用していますが、2階の各部屋も
設定温度(25℃)通りの室温で安定し、湿度も55%前後で快適です。
『小屋裏エアコンは難しい』で検索するとたくさんの記事が出て来ます。
内容は、
(1)冷気を各部屋に分配できない
(2)設定温度通りの温度にならない
(3)逆転結露が心配
などです。
理由として、床下エアコン暖房の様に幾つかの工夫(気密性能と基礎断熱、
それに床下の空気の流れを阻害する基礎の立上りレイアウト)で解決できない
自然現象の難しさがあるためです。
(1)冷気を各部屋に分配できない
ダクトと送風ファンを使って各部屋に冷気を分配する方法を取る場合、
ダクト内の汚れやカビが心配になります。
(2)設定温度通りの温度にならない
室温が設定温度になる前にエアコン本体のセンサーが働いてしまう。
或は、戻り(リターン)空気が取り込めず、場所により温度ムラが生じる。
(3)逆転結露が心配
気温30℃相対湿度80%の外気が壁や屋根の断熱材に侵入すると室温26℃で
露点に達してしまう計算になり、エアコンのある小屋裏の壁や屋根の中で
逆転結露を起こしてしまう。
(実際は、外気がそのまま壁や屋根内に侵入する訳ではなく、露点温度ももう少し低い温度と考えれるるが、
小屋裏を冷やさないと下階に冷気を届けられないので、出来れば20℃程度までは下げたい。)

上記の例では、壁の中の空気が28℃・相対湿度70%の場合、室温19℃以下で壁内の室内側が結露する。
特に(3)の逆転結露には注意を払わなければなりません。
弊社モデルハウスでは、通年での壁内・屋根内の温湿度を実測しており、
季節によって外気の影響がどの様に構造体、特に壁や屋根の内側に影響が
あるか調べています。

この様に小屋裏エアコンで全館冷房する場合、湿度と温度、冷気の届く距離に
難しさがあります。
この全てを解決するには、温度と湿度と流量(送風量)を適切にコントロール
しなければなりません。
その為の技術として、
(1)透湿性のある気密施工
(2)透湿性のある屋根防水と通気層
(3)外だし室温センサー
(4)流量(送風量)コントロール
がなければ、小屋裏エアコンを実現できないのです。
やっぱり、小屋裏エアコンは難しいですね。
でも、サンキハウスでは実現していますよ。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年06月19日
小屋裏エアコン始動
今年は梅雨入りが少し遅く、気温も低めで過ごしやすい日々が続いています。
梅雨の期間も短めと言う予報も出ていて助かりますね。
工事に影響が出ない様に祈っていますが、6月の半ばを過ぎてムシムシ感は
高くなってきました。
そこで、モデルハウスに装備した『小屋裏エアコン』をいよいよ使い始めました。
小屋裏エアコンとは、(過去の記事で説明していますので、ご覧ください。)
①「エアコン1台で全館冷房」・・・小屋裏エアコンの一般的な説明
②「暑さを防ぐ、2重屋根工法(2)」・・・小屋裏エアコンが危険な理由
③「小屋裏エアコン冷房、夏終わったけど」・・・モデルハウス実装の様子
②の「暑さを防ぐ、2重屋根工法(2)」で説明した様に、キンキンに冷えた
小屋裏空間は屋根からの熱と湿度によって結露を起こすリスクがあります。
その為、床下エアコン暖房より難しいと言われています。
試行錯誤を重ねた結果、このオリジナルなシステムを考案しました。
見える所だけ説明しますと、
エアコンで冷えた空気を写真の様にガラリを経由して各居室に届ける仕組みです。

他社との比較としては、ダクトとファンによって各部屋に冷風を配るのでなく、
小屋裏空間から直接各部屋に冷風を配る点が違います。
ダクト内の汚れを心配する必要がない点がメリット。
デメリットはちゃんと冷風が届くのか、冷房が効くのかと言う点です。
写真を真似して小屋裏空間に壁掛けエアコンを設置するだけではダメですよ。
(風量も足りないですし、温度差が大きく結露リスクが高まります。)
この辺りは企業秘密なので、ブログでは書けません。
詳しくお知りになりたい方はぜひ聖一色モデルハウスをお訪ね下さい。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
梅雨の期間も短めと言う予報も出ていて助かりますね。
工事に影響が出ない様に祈っていますが、6月の半ばを過ぎてムシムシ感は
高くなってきました。
そこで、モデルハウスに装備した『小屋裏エアコン』をいよいよ使い始めました。
小屋裏エアコンとは、(過去の記事で説明していますので、ご覧ください。)
①「エアコン1台で全館冷房」・・・小屋裏エアコンの一般的な説明
②「暑さを防ぐ、2重屋根工法(2)」・・・小屋裏エアコンが危険な理由
③「小屋裏エアコン冷房、夏終わったけど」・・・モデルハウス実装の様子
②の「暑さを防ぐ、2重屋根工法(2)」で説明した様に、キンキンに冷えた
小屋裏空間は屋根からの熱と湿度によって結露を起こすリスクがあります。
その為、床下エアコン暖房より難しいと言われています。
試行錯誤を重ねた結果、このオリジナルなシステムを考案しました。
見える所だけ説明しますと、
エアコンで冷えた空気を写真の様にガラリを経由して各居室に届ける仕組みです。

他社との比較としては、ダクトとファンによって各部屋に冷風を配るのでなく、
小屋裏空間から直接各部屋に冷風を配る点が違います。
ダクト内の汚れを心配する必要がない点がメリット。
デメリットはちゃんと冷風が届くのか、冷房が効くのかと言う点です。
写真を真似して小屋裏空間に壁掛けエアコンを設置するだけではダメですよ。
(風量も足りないですし、温度差が大きく結露リスクが高まります。)
この辺りは企業秘密なので、ブログでは書けません。
詳しくお知りになりたい方はぜひ聖一色モデルハウスをお訪ね下さい。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年03月20日
これ何~んだ。「防水編」
「これ何~んだ」シリーズは完成すると見えない部材や施工方法に焦点をあてた記事です。
お客様にはなじみのないモノですが、それぞれ重要な役目があり、価格も品質も様々です。
弊社では60年に耐えうる部材と施工方法をコスパと言う視点で考えて選択しています。
コスパはイニシャルコストだけでなくランニングコストも考えたものであるべきです。
最初は少しコストアップでも、60年の間に何度メンテナンスするかも考えましょう。
「これ何~んだ」シリーズの4回目は屋根の防水部材を取り上げます。
今回ご紹介するアスファルトルーフィングは屋根材によって隠れる部材です。
また、その存在もお施主様は知られていません。
屋根材には瓦、金属など色々な種類があります。
太陽の日射に耐え、風に耐え、地震にも耐えて家を雨から守る機能が必要ですが、
屋根材だけでは心配なので、その下に2段階目の防水層があります。
それがアスファルトルーフィングです。
図解すると

石川商店のHPから
目立たない部材のためか、その品質や性能にこだわる方は多くありません。
その為、安価なものを選んでいる工務店も多いのが実情です。
我々プロでも、全ての種類を試したわけではないですし、30年待たないと
結果は出ないので、判断が難しい部材でもあります。
そんな部材ですが、石川商店のHPで様々な検証が行われているのでご紹介します。

石川商店のHP
最終的に石川商店が選んだのはこちらです。
「田島のニューライナールーフィング」は田島のルーフィング商品では2番目に高価な部材です。
何故、2番目が良いかと言うと、石川商店のHPを見て下さい。

もちろん弊社の使用しているアスファルトルーフィングは田島のニューライナールーフィングです。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
お客様にはなじみのないモノですが、それぞれ重要な役目があり、価格も品質も様々です。
弊社では60年に耐えうる部材と施工方法をコスパと言う視点で考えて選択しています。
コスパはイニシャルコストだけでなくランニングコストも考えたものであるべきです。
最初は少しコストアップでも、60年の間に何度メンテナンスするかも考えましょう。
「これ何~んだ」シリーズの4回目は屋根の防水部材を取り上げます。
今回ご紹介するアスファルトルーフィングは屋根材によって隠れる部材です。
また、その存在もお施主様は知られていません。
屋根材には瓦、金属など色々な種類があります。
太陽の日射に耐え、風に耐え、地震にも耐えて家を雨から守る機能が必要ですが、
屋根材だけでは心配なので、その下に2段階目の防水層があります。
それがアスファルトルーフィングです。
図解すると

石川商店のHPから
目立たない部材のためか、その品質や性能にこだわる方は多くありません。
その為、安価なものを選んでいる工務店も多いのが実情です。
我々プロでも、全ての種類を試したわけではないですし、30年待たないと
結果は出ないので、判断が難しい部材でもあります。
そんな部材ですが、石川商店のHPで様々な検証が行われているのでご紹介します。

石川商店のHP
最終的に石川商店が選んだのはこちらです。
「田島のニューライナールーフィング」は田島のルーフィング商品では2番目に高価な部材です。
何故、2番目が良いかと言うと、石川商店のHPを見て下さい。

もちろん弊社の使用しているアスファルトルーフィングは田島のニューライナールーフィングです。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
タグ :改質アスファルトルーフィング
2022年03月13日
遮熱対策の「これ何~んだ」
今日は気温が23℃もあり、上着が要らないくらいの陽気ですね。
そうなると床下エアコンの話題も季節はずれ。 お伝えするネタがない。
では、と言う事で
夏の話題を考えていたら、ありました他社ではやってない「これ何~んだ」

写真を見ても何の事か分かりませんよね。 これは屋根の部分です。
まだ合板(野地板)を張ってないので、天井の部分が見えていて、
シルバータイベックが張ってあります。
シルバータイベックの下は天井用の断熱材があるのですが、
この写真からは見えません。(このブログの最後の写真でご覧になれます。)
天井には断熱材が必要です。
なぜなら夏は屋根が70℃以上にもなり、その暑さが天井に伝わるからです。
天井に断熱材を敷き込むのですが、断熱材の種類によって姿はまちまち。
普通の住宅はこんな感じ

袋入りの断熱材が天井の上に敷き込まれています。
流行のセルロースファイバーの吹込み断熱材はこんな感じ。

ホコリが積もった様な感じですが、新聞紙のリサイクルの
セルロースファイバーを玉状にして吹込みます。
断熱材は断熱はするけど、それ自体が熱を蓄えてしまうと室内に熱を放射します。
そこで、断熱材の湿気を排出し、熱の源である赤外線を反射するタイベックシルバー
を天井断熱材の上に敷いてあげれば、遮熱効果のある密閉状態の断熱層が出来ます。
それを図解するとこんな感じ、

この下には勿論分厚い断熱材が二重に敷いてあります。
この様に二重に断熱材を敷き込みます。

いかがですか。
普段は見えない所ですが、きっちり対策を施した住宅は夏の暑さも無縁です。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
そうなると床下エアコンの話題も季節はずれ。 お伝えするネタがない。
では、と言う事で
夏の話題を考えていたら、ありました他社ではやってない「これ何~んだ」

写真を見ても何の事か分かりませんよね。 これは屋根の部分です。
まだ合板(野地板)を張ってないので、天井の部分が見えていて、
シルバータイベックが張ってあります。
シルバータイベックの下は天井用の断熱材があるのですが、
この写真からは見えません。(このブログの最後の写真でご覧になれます。)
天井には断熱材が必要です。
なぜなら夏は屋根が70℃以上にもなり、その暑さが天井に伝わるからです。
天井に断熱材を敷き込むのですが、断熱材の種類によって姿はまちまち。
普通の住宅はこんな感じ

袋入りの断熱材が天井の上に敷き込まれています。
流行のセルロースファイバーの吹込み断熱材はこんな感じ。

ホコリが積もった様な感じですが、新聞紙のリサイクルの
セルロースファイバーを玉状にして吹込みます。
でもこれって粉が天井から室内に落ち来たらと心配になります。
気密シートを断熱材と天井の間に敷いてあれば良いのですが、セルロース
ファイバーを湿度調整に使う考えの住宅には気密シートがありませんのでね。
断熱材は断熱はするけど、それ自体が熱を蓄えてしまうと室内に熱を放射します。
そこで、断熱材の湿気を排出し、熱の源である赤外線を反射するタイベックシルバー
を天井断熱材の上に敷いてあげれば、遮熱効果のある密閉状態の断熱層が出来ます。
それを図解するとこんな感じ、

この下には勿論分厚い断熱材が二重に敷いてあります。
この様に二重に断熱材を敷き込みます。

いかがですか。
普段は見えない所ですが、きっちり対策を施した住宅は夏の暑さも無縁です。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年02月27日
これ何~んだ?第2弾
ロシア軍がウクライナに侵攻しました。
北方領土が返って来ると信じていた日本の高官も目が覚めたでしょう。
世界は甘くはないって事が改めて分かりました。
日本はエネルギーの問題をもっと前倒しで進めなければなりません。
原発は嫌だけれども、石油依存から脱却するためには再稼働もやむなし、
再生可能エネルギーに早く転換しなければならないと考えます。






前回の「これ何~んだ?」の第2弾です。
やはり気密を取るための部材ですが、「先張り気密シート」と言います。
何が「先張り」かと言うと、気密を取る為に先に挟んで仕込んで置くからです。

室内壁を建てる前に気密シートを張る
この様に外壁と間仕切り壁が交差する部分に、前もって気密シートを挟んで置き
気密ラインを連続させます。

連続すると外気の進入(隙間風)がより少なくなるので保温が効き暖かいのです。
内装工事の段階になると、断熱材を壁の中一杯に入れて、気密シートを張ります。
その際、先張り気密シートと重ね合わせて気密ラインを繋げます。

こうする事で横方向は気密ラインが連続しますので、気密テープもいらずに
気密処理は完成します。
建方時に挟んで置くという手間はありますが、気密が完全に取れるので
弊社では必ず行っています。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
北方領土が返って来ると信じていた日本の高官も目が覚めたでしょう。
世界は甘くはないって事が改めて分かりました。
日本はエネルギーの問題をもっと前倒しで進めなければなりません。
原発は嫌だけれども、石油依存から脱却するためには再稼働もやむなし、
再生可能エネルギーに早く転換しなければならないと考えます。






前回の「これ何~んだ?」の第2弾です。
やはり気密を取るための部材ですが、「先張り気密シート」と言います。
何が「先張り」かと言うと、気密を取る為に先に挟んで仕込んで置くからです。

室内壁を建てる前に気密シートを張る
この様に外壁と間仕切り壁が交差する部分に、前もって気密シートを挟んで置き
気密ラインを連続させます。

連続すると外気の進入(隙間風)がより少なくなるので保温が効き暖かいのです。
内装工事の段階になると、断熱材を壁の中一杯に入れて、気密シートを張ります。
その際、先張り気密シートと重ね合わせて気密ラインを繋げます。

こうする事で横方向は気密ラインが連続しますので、気密テープもいらずに
気密処理は完成します。
建方時に挟んで置くという手間はありますが、気密が完全に取れるので
弊社では必ず行っています。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
現在お知らせするイベントはありません。
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年02月19日
これ何~んだ?
カーリング女子の活躍が凄いですね。
前回の冬のオリンピックで銅メダルを取っていますが、同じメンバーで
今回は銀メダル以上が確定しました。
代表決定戦では北海道銀行の女子カーリングチームに接戦の末に勝ち
前回と同じロコ・ソラーレが日本代表になったのですが、
日本の女子カーリングチームは世界レベルと言う事ですね。
決勝が楽しみです。 銀とは言わず、ぜひ🥇メダルを取って欲しいです。
🥌 🥌 🥌 🥌 🥌
さて、今日の話題は「これ何~んだ?」です。

豆腐のケースの様な形ですが、サンキハウスの家では必需品です。
弊社は気密性能を高めた、高断熱住宅を建てていますが、それには
この様な気密のための部材が色々必要です。
数ある部材の中で、チョット変わったものなので紹介します。
これはコンセントやスイッチを包む気密カバーです。
電線は家の隅々に配線されていますが、最後には家の外の電柱に
繋げられる宿命上、外に向かって隙間を作ってしまう為、気密に
とっては厄介なものです。
ですから、普通に電線を這わせてコンセントやスイッチを壁に設置
すると、そこから隙間風(外気)が進入してきます。
このカバーを先に壁に付けます。
するとこの様になります。

勿論、断熱材を押しつぶしてはいけません。
箱の厚み分だけ切り取って付けます。(透明なので裏に断熱材が見えますね。)
電線の為の穴をチョットだけ開けて、電線を通しておきます。
そして、コンセント(スイッチ)ケースを取り付けます。

この後、石膏ボードで壁を塞いで、内装仕上げ(クロスや塗り壁)をします。
内装仕上げが済んだら、壁に穴を開けてコンセント(スイッチ)プレートを
付けて終わりです。
弊社では気密測定を全棟で実施しています。
C値≦0.5c㎡/㎡(2x6)をお約束していますが、平均は0.3c㎡/㎡位だと
思います。
小さければ小さい程良いとは言えませんが、1.0c㎡/㎡を越えると
換気をコントロールできないと考えています。
換気をコントロールできないと、空気の淀んだ部屋や空間ができてしまい、
人間にも建物にも良いことはありません。
特に今の様に寒い真冬と真夏は窓を開けませんので、換気が大事になります。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
R4 2/26(土)・2/27(日) 床下エアコン体験会♪
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
前回の冬のオリンピックで銅メダルを取っていますが、同じメンバーで
今回は銀メダル以上が確定しました。
代表決定戦では北海道銀行の女子カーリングチームに接戦の末に勝ち
前回と同じロコ・ソラーレが日本代表になったのですが、
日本の女子カーリングチームは世界レベルと言う事ですね。
決勝が楽しみです。 銀とは言わず、ぜひ🥇メダルを取って欲しいです。
🥌 🥌 🥌 🥌 🥌
さて、今日の話題は「これ何~んだ?」です。

豆腐のケースの様な形ですが、サンキハウスの家では必需品です。
弊社は気密性能を高めた、高断熱住宅を建てていますが、それには
この様な気密のための部材が色々必要です。
数ある部材の中で、チョット変わったものなので紹介します。
これはコンセントやスイッチを包む気密カバーです。
電線は家の隅々に配線されていますが、最後には家の外の電柱に
繋げられる宿命上、外に向かって隙間を作ってしまう為、気密に
とっては厄介なものです。
ですから、普通に電線を這わせてコンセントやスイッチを壁に設置
すると、そこから隙間風(外気)が進入してきます。
このカバーを先に壁に付けます。
するとこの様になります。

勿論、断熱材を押しつぶしてはいけません。
箱の厚み分だけ切り取って付けます。(透明なので裏に断熱材が見えますね。)
電線の為の穴をチョットだけ開けて、電線を通しておきます。
そして、コンセント(スイッチ)ケースを取り付けます。

この後、石膏ボードで壁を塞いで、内装仕上げ(クロスや塗り壁)をします。
内装仕上げが済んだら、壁に穴を開けてコンセント(スイッチ)プレートを
付けて終わりです。
弊社では気密測定を全棟で実施しています。
C値≦0.5c㎡/㎡(2x6)をお約束していますが、平均は0.3c㎡/㎡位だと
思います。
小さければ小さい程良いとは言えませんが、1.0c㎡/㎡を越えると
換気をコントロールできないと考えています。
換気をコントロールできないと、空気の淀んだ部屋や空間ができてしまい、
人間にも建物にも良いことはありません。
特に今の様に寒い真冬と真夏は窓を開けませんので、換気が大事になります。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
R4 2/26(土)・2/27(日) 床下エアコン体験会♪
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年01月30日
床下エアコンに異変が!第2弾
今週末は富士市で完成見学会を行っております。
初の平屋と言う事もあり、多くの方にご覧いただきました。😁

しかし、昨日最後のチェックに行ったところ、家があまり暖かくない事に気付きました。
床下エアコン自体は運転をしているのですが、出て来る暖気もぬるい感じで、
家も正直暖かいって感じでなく、「寒くはないね。」程度で、これではお見せ出来ません。
前回のブログ記事「床下エアコンに異変が!」での我が家の様に床下エアコンにホコリが
溜っている分けでもないし(新築なのであり得えない)なぜだろうと設定温度を確かめる為、
壁のコントローラを探しました。
すると、

「あれ、コントローラがない。」
すぐさま監督に電話すると、「半導体不足で欠品しています。」
「お引渡しまでには間に合いますが、今週末はムリです。」との返事。
「普通の無線リモコンでエアコンは付きますから、大丈夫じゃないですか。」
私「それがダメなんだよね。」「これじゃ温度が上がらないから。」
監督「えっ何故ですか?」
私「それはね、・・・。」、・・・と言う訳でこのブログ記事で説明します。
エアコン本体はこの様に床に埋め込まれています。

そして、上の画像の〇の中にあるセンサーで室温を測り、設定温度になると
サーモが働いてアイドル運転になったり、室温が下がると運転が活発になったりします。
普通の使い方「壁に設置して、その部屋を暖める(冷やす)」ならこの本体センサーで
問題ありません。
しかし、床下エアコンとして使うなら、これではダメです。👎
床下エアコンは、設置位置からその本体の下と上では5℃~10℃位の温度差が生じます。
また、出来るだけ設置位置に隙間を作らない事が大事なのですが、完全に隙間を無くす
ことは出来ません。(少しは隙間がないと設置できないため。)

すると、少しある隙間から床下の暖気が漏れてきて、エアコンの本体センサーが
反応して、アイドル運転にしてしまうのです。(サーモが効いて運転を止めてしまう。)
この事をショートサーキットと呼びます。
これを避ける為、エアコン本体のセンサーを使わず、離れた所で温度を取り、その温度を
室温として床下エアコンの出力を制御しなければなりません。
それがこれです。

このセンサー付き有線コントローラーを室温調整したい部屋に設置すれば、
その場所での室温を設定温度に近づけてくれます。
今回そのワイアードリモコン(有線コントローラー)が付いていないので
床下エアコンはアイドル運転になってしまい、部屋を暖められないのです。
「恐ろしや半導体不足!」です。
「何だ、床下エアコンって大して暖かくないじゃん」との悪い評判にならない様に
ブログ記事にしました。
ちゃんと動いている床下エアコンはいつでも弊社の「聖一色モデルハウス」で
ご覧戴けますので、ご興味のある方はご連絡下さい。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
R4 2/5(土)・2/6(日)『子育てが楽しくなる。大人可愛いお家』完成見学会
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
初の平屋と言う事もあり、多くの方にご覧いただきました。😁

しかし、昨日最後のチェックに行ったところ、家があまり暖かくない事に気付きました。
床下エアコン自体は運転をしているのですが、出て来る暖気もぬるい感じで、
家も正直暖かいって感じでなく、「寒くはないね。」程度で、これではお見せ出来ません。
前回のブログ記事「床下エアコンに異変が!」での我が家の様に床下エアコンにホコリが
溜っている分けでもないし(新築なのであり得えない)なぜだろうと設定温度を確かめる為、
壁のコントローラを探しました。
すると、

「あれ、コントローラがない。」
すぐさま監督に電話すると、「半導体不足で欠品しています。」
「お引渡しまでには間に合いますが、今週末はムリです。」との返事。
「普通の無線リモコンでエアコンは付きますから、大丈夫じゃないですか。」
私「それがダメなんだよね。」「これじゃ温度が上がらないから。」
監督「えっ何故ですか?」
私「それはね、・・・。」、・・・と言う訳でこのブログ記事で説明します。
エアコン本体はこの様に床に埋め込まれています。

そして、上の画像の〇の中にあるセンサーで室温を測り、設定温度になると
サーモが働いてアイドル運転になったり、室温が下がると運転が活発になったりします。
普通の使い方「壁に設置して、その部屋を暖める(冷やす)」ならこの本体センサーで
問題ありません。
しかし、床下エアコンとして使うなら、これではダメです。👎
床下エアコンは、設置位置からその本体の下と上では5℃~10℃位の温度差が生じます。
また、出来るだけ設置位置に隙間を作らない事が大事なのですが、完全に隙間を無くす
ことは出来ません。(少しは隙間がないと設置できないため。)

すると、少しある隙間から床下の暖気が漏れてきて、エアコンの本体センサーが
反応して、アイドル運転にしてしまうのです。(サーモが効いて運転を止めてしまう。)
この事をショートサーキットと呼びます。
これを避ける為、エアコン本体のセンサーを使わず、離れた所で温度を取り、その温度を
室温として床下エアコンの出力を制御しなければなりません。
それがこれです。

このセンサー付き有線コントローラーを室温調整したい部屋に設置すれば、
その場所での室温を設定温度に近づけてくれます。
今回そのワイアードリモコン(有線コントローラー)が付いていないので
床下エアコンはアイドル運転になってしまい、部屋を暖められないのです。
「恐ろしや半導体不足!」です。
「何だ、床下エアコンって大して暖かくないじゃん」との悪い評判にならない様に
ブログ記事にしました。
ちゃんと動いている床下エアコンはいつでも弊社の「聖一色モデルハウス」で
ご覧戴けますので、ご興味のある方はご連絡下さい。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
R4 2/5(土)・2/6(日)『子育てが楽しくなる。大人可愛いお家』完成見学会
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
2022年01月09日
わが家の窓に結露発生!
2022年初めての投稿です。 今年もよろしくお願いします。
さて、今年は寒い日が多いですね。
スキーを嗜む私としては、雪が多いので楽しみも多いのですが、日々の寒さはつらい所です。
自邸は15年ほど前に2x4壁とペアガラスの樹脂サッシで建てたツーバイフォー住宅です。
現在なら2x6壁とトリプルガラスの樹脂サッシで建てたと思うのですが、その当時は
トリプルガラスの樹脂サッシが国産では存在しなかった為、そうなりました。
この所、室内が乾燥状態にあり、インフルエンザなどの予防のためにも加湿器を使って
50%近くまで相対湿度を上げています。(1F居間、上の段です。下の段は床下エアコン)

寝室は夫婦二人が同室で就寝している為か、より高い60%程度まで湿度が上がっていました。
その為か、寝室の窓が結露してしまいました。😆

普段、樹脂サッシは結露しないと言っておきながら、結露を起こしてしまったので、
正直に告白しました。(笑)
因みにガラスは結露していますが、窓枠(樹脂の白い所)は結露していません。
結露は自然現象なので、条件が整えば発生します。
今朝の室温は約19℃、相対湿度は約60%でしたので、結露するためにはガラスの温度が
11℃以下にまで下がっていたと計算できます。
外気温が氷点下近くまで下がっていたので、ガラスの温度が11℃付近まで下がってしまった
のでしょう。
現在の最高峰であるトリプルガラスの樹脂サッシなら結露しなかったかも知れません。
しかし、冬の過乾燥の為に加湿器を使って加湿しすぎると、トリプルガラスと言えども、
ガラスの表面がうっすらと結露する事は考えられます。
あくまで、相対湿度と室温、それにガラスの表面温度によって生ずる自然現象ですので、
結露させない為には日々の室温と湿度の管理が必要と言う事になります。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家
さて、今年は寒い日が多いですね。
スキーを嗜む私としては、雪が多いので楽しみも多いのですが、日々の寒さはつらい所です。
自邸は15年ほど前に2x4壁とペアガラスの樹脂サッシで建てたツーバイフォー住宅です。
現在なら2x6壁とトリプルガラスの樹脂サッシで建てたと思うのですが、その当時は
トリプルガラスの樹脂サッシが国産では存在しなかった為、そうなりました。
この所、室内が乾燥状態にあり、インフルエンザなどの予防のためにも加湿器を使って
50%近くまで相対湿度を上げています。(1F居間、上の段です。下の段は床下エアコン)

寝室は夫婦二人が同室で就寝している為か、より高い60%程度まで湿度が上がっていました。
その為か、寝室の窓が結露してしまいました。😆

普段、樹脂サッシは結露しないと言っておきながら、結露を起こしてしまったので、
正直に告白しました。(笑)
因みにガラスは結露していますが、窓枠(樹脂の白い所)は結露していません。
結露は自然現象なので、条件が整えば発生します。
今朝の室温は約19℃、相対湿度は約60%でしたので、結露するためにはガラスの温度が
11℃以下にまで下がっていたと計算できます。
外気温が氷点下近くまで下がっていたので、ガラスの温度が11℃付近まで下がってしまった
のでしょう。
現在の最高峰であるトリプルガラスの樹脂サッシなら結露しなかったかも知れません。
しかし、冬の過乾燥の為に加湿器を使って加湿しすぎると、トリプルガラスと言えども、
ガラスの表面がうっすらと結露する事は考えられます。
あくまで、相対湿度と室温、それにガラスの表面温度によって生ずる自然現象ですので、
結露させない為には日々の室温と湿度の管理が必要と言う事になります。☘️
▲▼▲▼▲ イベントのお知らせ ▲▼▲▼▲
☆ ★ ☆ サンキハウスの施工事例 ☆ ★ ☆
大好きなカフェの居心地が叶う家
北欧テイストと住み心地、どちらも叶えたナチュラルハウス
マリメッコのファブリックや北欧家具の映える北欧スタイルの家
スタイル+耐震+省エネの大変身リノベーション
リノベーションで生まれ変わった築22年の家